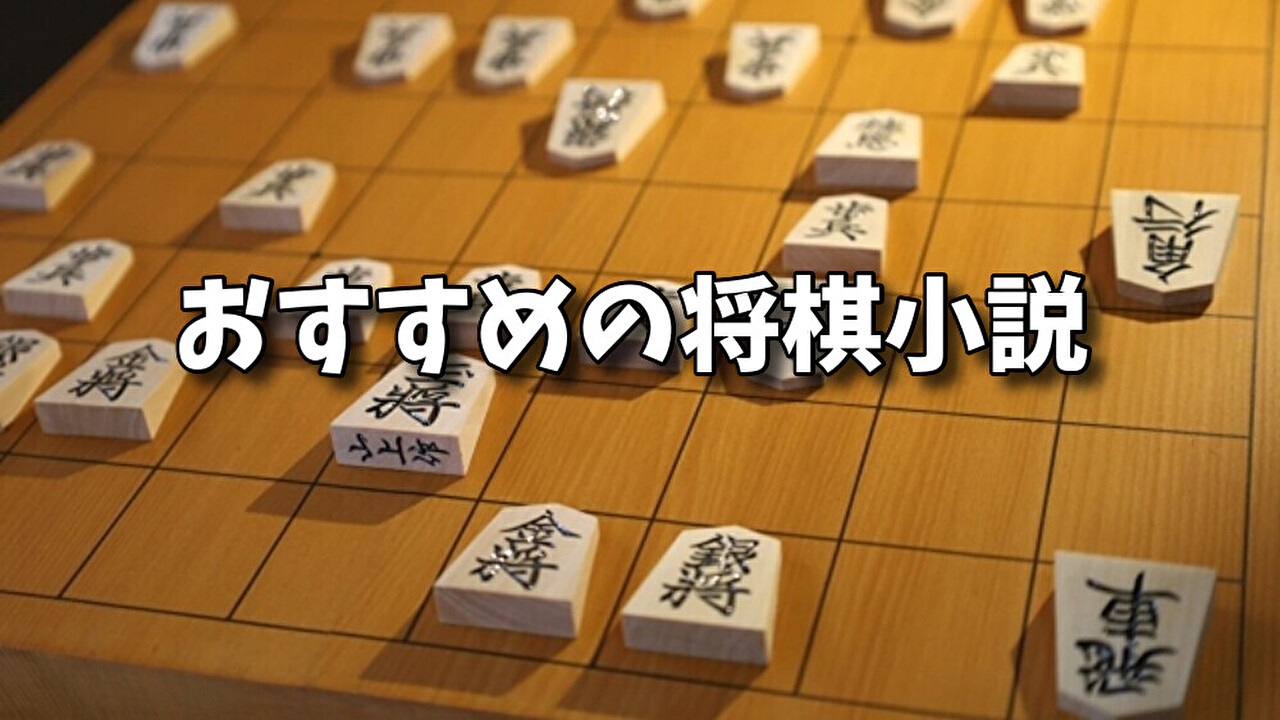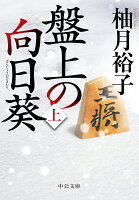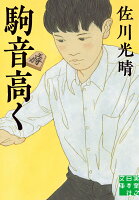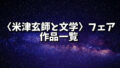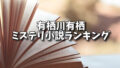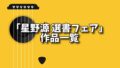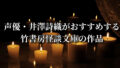菊池寛や坂口安吾など将棋好きの作家はむかしから多く、文壇と将棋界の交流も盛んにおこなわれてきましたが、近年(2010年代後半以降)はとくに将棋ブームの影響もあり、話題になる将棋小説が増えたように思います。
そこでこの記事では、おすすめの将棋小説を12作紹介いたします。元奨励会員による本格的な将棋小説や重厚なミステリ、人情味あふれる青春小説・家族小説などいろいろなタイプの作品がありますので、本選びの参考になれば幸いです。
『覇王の譜』橋本長道
「お前は一流にはなれんよ」。七年間、C級2組から這い上がれない直江大に剛力英明王座はそう言い放つ。旧友との目も眩むような格差。だが、天才少年との邂逅、“孤剣”の異名を持つ師の特訓が、燻っていた直江を覚醒させる。彼の進む道の先には運命の対局が待ち受けていた。元奨励会会員、将棋を深く知る著者が青年棋士の成長と個性あふれる棋士群像を描く。魂震わす将棋エンターテインメント。
(新潮社HPより引用)
『覇王の譜』は、元奨励会員である橋本長道による長編小説です。将棋界の底辺でくすぶりつづける主人公の再起を描いた物語で、個人的には日本でいちばん──ということは世界でいちばんおもしろい将棋小説だと思います。将棋を題材にするなら、プロ棋士の世界を描くならこうであってほしい、という理想を完璧に具現化してくれた作品です。
著者が元奨励会員ということで対局シーンのリアリティは折り紙つき。棋士の心理描写から、ちょっとした用語の使い方までまったく隙がありません。また、主人公のライバルである剛力、友人の女流棋士・紗香、師匠の師村など魅力的な脇役も多数登場し、物語に厚みと彩りを与えてくれます。こうしたキャラクター造形の見事さについては、著者が元奨励会員であることなど関係なく、たんに小説家として確かな実力があることの証左でしょう。
プロ棋士の世界をここまで描いた作品はなかなかないので、将棋小説に興味がありながらまだ読んでいないという方がいるなら、絶対に手にとっていただきたい傑作です。
『死神の棋譜』奥泉光
初夏、名人戦の最中に詰将棋の矢文が見つかった。その「不詰めの図式」を将棋会館に持ち込んだ元奨励会員・夏尾は消息を絶つ。将棋ライターの〈私〉は、同業者の天谷から22年前の失踪事件との奇妙な符合を告げられ、かつての天谷のように謎を追い始めるが──。幻の「棋道会」、北海道の廃坑、地下神殿での因縁の対局。将棋に魅入られた者の渇望と息もつかせぬ展開が交錯する究極のミステリ!
(新潮社HPより引用)
『死神の棋譜』は、芥川賞作家・奥泉光による長編小説です。純文学のなかにミステリやSFの要素を取り入れた作品を多く発表している著者ですが、本作もエンタテインメント性の高い将棋ミステリとなっています。
「不詰の詰将棋」にまつわる失踪事件の謎を、元奨励会員で将棋ライターの主人公が追うというのがストーリーの軸で、棋道会(別名魔道会)と呼ばれる団体と、奇妙な駒を使った「龍神棋」を巡る幻想小説としての側面もあります。将棋というゲームの業の深さや魔性を描き、かつてプロ棋士になる道を絶たれた主人公の極限の心理をえぐり出す、そんな危険な緊張感をはらんだ傑作です。
著者は長年の将棋ファンであり、名人戦の観戦記の執筆経験もあるということで、将棋にまつわる描写もさすがのひと言。冒頭から羽生善治、森内俊之といった実在の棋士の名前が出てくるところも将棋ファンの興味をそそるところだと思います。
『神の悪手』芦沢央
俺はなぜ、もっと早く引き返さなかったのか──。棋士を目指して13歳で奨励会に入会した岩城啓一だったが、20歳をとうに過ぎた現在もプロ入りを果たせずにいた。9期目となった三段リーグ最終日前日の夕刻、翌日対局する村尾が突然訪ねてくる。今期が昇段のラストチャンスとなった村尾が啓一に告げたのは……。夢を追うことの恍惚と苦悩、誰とも分かち合えない孤独を深く刻むミステリ5編。
(新潮社HPより引用)
『神の悪手』は、芦沢央による短編集です。収録作5編すべてが将棋を題材にしています。奨励会、詰将棋、タイトル戦、駒師など将棋にまつわる種々のテーマを各編で扱っており、将棋好きにとって満足度の高い一冊だと思います。
先輩を過失で殺してしまった奨励会員の葛藤を描く表題作「神の悪手」がいちばん出来がいいと思いますが、個人的に好きなのは不思議な詰将棋を作る少年の物語「ミイラ」です。詰将棋の謎が解ける同時に少年の抱えてきたドラマが浮かびあがり、はっと胸を突かれる感動的な一編です。
なお、文庫発売時の帯には「このどんでん返しが切なすぎる!!」とあり、そうした惹句があると売れやすいのはわかるのですが、誤解を招きかねない文言だと思います。ミステリとして読める作品が多いことは間違いないですが、叙述トリックのような派手などんでん返しは狙った作品集ではありません。
『おまえレベルの話はしてない』芦沢央
小学生の頃から、棋士という夢を追って切磋琢磨してきた芝と大島。芝は夢を叶えたものの成績が低迷、一方の大島は夢を諦め弁護士になった。道が分かれたからこそ、今も消えない互いへの嫉妬、羨望、侮蔑。2人の行方にあるのは、光か闇か?
(「BOOK」データベースより引用)
『おまえレベルの話はしてない』は、芦沢央による長編小説です。前述の『神の悪手』の著者である彼女が、今度は長編(やや短めですが)で、かつミステリ的な手法にこだわらず将棋をテーマのど真ん中に据えて挑んだ作品。他の仕事をすべてストップにし、2年かけて執筆したという渾身の一作です。
主人公は奨励会員の同期である青年ふたり。念願のプロ棋士になりながらも成績不振にあえぎ、孤独のなかでもがき苦しむ芝と、17歳で将棋の道を諦めて東大へ進学し、現在は弁護士として活躍しながら、いまだ将棋のことを引きずりつづける大島。物語は彼らのそれぞれの視点から語られる二部構成となっています。
著者の従来の持ち味が遺憾なく発揮された大島の章もすばらしいですが、白眉は第一部である芝の章でしょう。将棋界の厳しさに苦しみ、追い詰められ、壊れていきそうな芝のリアルな日々を、ふだんとは異なる文体を用いて純文学的に描きだす趣向はお見事のひと言。プロ棋士の極限の姿をえぐりだした傑作です。
『無月の譜』松浦泰輝
「別次元の輝きだった。手に取って一枚一枚じっくりと見る前から、駒がざらりと散らばったあたりが、すでに仄かな光に包まれているように見えた」戦死した駒師が遺した傑作はどこへ? 棋士の夢破れた青年が、再起をかけてその行方を追う。失われた駒を求めて、東京からシンガポール、マレーシア、アメリカへ──旅の終わりに青年・竜介がたどり着いた真実とは? 松浦文学のあらたな到達点。幻の将棋駒をめぐる希望と再生の物語です。
(毎日新聞出版HPより引用)
『無月の譜』は、芥川賞作家・松浦泰輝による長編小説です。主人公はプロ棋士の夢を絶たれた元奨励会員。失意のなか、かつて戦死した大叔父がじつは将棋の駒を作る駒師だったことを彼は知り、やがて大叔父の遺作である幻の名駒があるかもしれないとわかると、その駒を探し求める旅へ出ます。大叔父の生涯を紐解いていく過程と、駒を探して海外まで飛びだしていく旅路を丁寧に追い、夢破れた主人公が再起していくさまを描いた力作です。
基本的にはロードノベルなので、将棋の知識がゼロでも通読にまったく問題はないでしょう。また、物語の主要部分は1998年から始まりますが、プロローグは現代で、藤井聡太四段(当時)の29連勝(歴代最多連勝記録)のエピソードが重要なキーとして使われています。藤井聡太フィーバーから将棋に興味を持った方が手にとってみるのもいいかもしれません。
『盤上の向日葵』柚月裕子
平成六年、夏。埼玉県の山中で白骨死体が発見された。遺留品は、名匠の将棋駒。叩き上げの刑事・石破と、かつてプロ棋士を志した新米刑事の佐野は、駒の足取りを追って日本各地に飛ぶ。折しも将棋界では、実業界から転身した異端の天才棋士・上条桂介が、世紀の一戦に挑もうとしていた。
(中央公論新社HPより引用)
『盤上の向日葵』は、柚月裕子による長編小説です。山中で発見された男の白骨死体と遺留品の名駒の謎を刑事たちの捜査と、実業界から将棋界へ転身した天才棋士の半生を交互に描いていくミステリです。現在と過去がいかに交錯し、謎が解かれていくのかというサスペンスも見事ですが、将棋にとりつかれ、あるいは救われていく人間たちの様々なドラマが丁寧に描かれているところが魅力の作品です。
キャラクターもそれぞれに印象的ですが、なかでも抜群の存在感を放つのは真剣師・東明重慶でしょう。実在した小池重明をモデルにしたキャラクターなので、昭和の賭け将棋の世界に興味のある方も必読です。
『駒音高く』佐川光晴
「絶対棋士になってやる」と誓った中学1年生の祐也だが、次第に勝てなくなり学校の成績も落ちてきて……(「それでも、将棋が好きだ」)。青春・家族小説の名手が、プロを目指す中学生、引退間際の棋士、将棋会館の清掃員など、勝負の世界で歩みを進める人々のドラマを生き生きと描く珠玉の短編集。第31回将棋ペンクラブ大賞文芸部門優秀賞受賞作。
(実業之日本社HPより引用)
『駒音高く』は、佐川光晴による連作短編集です。全7話で、将棋会館の清掃員、将棋教室に通う小学生、研修会でプロを目指す中学生、プロ棋士を目指す娘の母親、奨励会員の青年、元奨励会員の新聞記者、元タイトルホルダーのベテラン棋士と、将棋にまつわる人々がそれぞれ各話の主人公を務めます。
どの短編においても登場人物への作者の眼差しは温かく、将棋の世界の厳しさが描かれる部分もありつつ、より将棋のポジティブな面にスポットが当てられた一冊です。全編がゆるりとつながっている構成もニクいところ。人情味あふれる将棋小説が読みたい方は必読です。
『踊り子と将棋指し』坂上琴
ある朝、横須賀の公園で目覚めた男は、呑み過ぎたせいか自分の名前すら思い出せない。聖良という女性が現れ、男は「三ちゃん」と呼ばれる。三ちゃんがどうやらアルコール依存症らしいとわかり、聖良の部屋に住まわせてもらうことに。聖良の本名は依子で、現役のストリッパー。しばらくして依子に大阪での仕事が入り、三ちゃんも同行。無難にマネージャー役をこなしていたが、大金が動く将棋の真剣勝負に巻き込まれてしまい……。
(講談社HPより引用)
『踊り子と将棋指し』は、坂上琴による長編小説です。2015年に第10回小説現代新人賞を受賞した著者のデビュー作(かつ、今のところ唯一の作品)で、記憶喪失になってしまったアルコール依存症の棋士と、とうが立ったストリッパーの女性の奇妙な共同生活を描いた物語です。
時代設定は書かれたときと同じく2015年頃だと思いますが、ストリッパーの地方巡業や旅先での賭け将棋といった要素もあいまって、昭和にタイムスリップしたような懐かしさを感じさせてくれます。筆致はとぼけたようなユーモアを漂わせ、人生の下り坂を迎えている男女を描きながらも、どこかほのぼのした独特の味わいがあるのも魅力。派手さはありませんが、市井の人々の温かさを感じられる佳品です。
なお、将棋ファンなら主人公の名前や初手に端歩を突く戦法からすぐわかるとおり、坂田(阪田)三吉がモデルになっています。
『僕は金になる』桂望実
小学六年の春、父ちゃんが姉ちゃんを連れて家を出た。ふたりは賭け将棋で気ままに暮らしている。姉ちゃんの将来を案じる僕は、会うたびにその日暮らしを咎めるのだが、楽しそうなふたりがどこか羨ましい。将棋の天才の姉ちゃんと、いたって普通の僕。ドラマチックな人生に憧れる僕は、なにかとやらかす父ちゃんと姉ちゃんを放っておけず……。心にしみる家族小説。
(祥伝社HPより引用)
『僕は金になる』は、桂望実による長編小説です。タイトルの「金」は「かね」ではなく、「きん」と読みます。ひとつの家族をめぐる大河小説で、1979年から2017年までが舞台。離婚した両親と、父親に引き取られた姉、母親に引き取られた主人公の物語で、将棋は姉が趣味で指しています。
父親は自分で働きもせず娘に賭け将棋をさせて生活の糧を得ており、主人公の心配をよそに彼らはそんな暮らしに満足している様子。一方、母親は母親で新しいパートナーを得ており、主人公はふたつに分かれた家族のあいだを行き来しながら年を重ねていきます。厳しい勝負の世界を描くというのではなく(そういうシーンも少しありますが)、ひと組の家族の物語に将棋が溶けこんでいる、ちょっと珍しいタイプの将棋小説です。
作中で40年弱の時間が流れますが、おおむね3~4年刻みで章が区切られ、ひとつの章につき文庫で30~40ページほど、全体で280ページほどなので、気軽に読みやすい分量です。熾烈な勝負の世界に疲れたら、ほのぼのと心にしみる家族小説を通じて将棋に触れてみるのもいいかもしれません。
『殺人の駒音』亜木冬彦
死神の異名をもつ八神香介。一三歳の天才棋士に敗れ、一度は挫折した男が、それから一六年後、将棋の表舞台に現われた。第五期竜将ランキング一回戦……それはアマチュア最高位から、プロ棋士に挑む、命をかけた戦いとなるはずだった。しかし対局当日、相手プロは姿を見せず、自宅で何者かに殺されていた! 卓越したストーリーと熱気で読者を魅了し、横溝正史賞史上初の特別賞を冠せられた、伝説の傑作。
(KADOKAWAHPより引用)
『殺人の駒音』は、亜木冬彦による長編小説です。第12回(1992年度)横溝正史賞の特別賞受賞作で、アマチュア参加の棋戦で真剣師と対局するはずだったプロ棋士たちが次々と事件に見舞われるミステリです。
全体的に古臭い部分があったり、ミステリとしての強度が物足りなかったり、弱点もある作品だと思いますが、将棋を指す男たち──とくに真剣師たちのドラマが熱い物語に仕上がっています。「死神」「傀儡師」といった面妖な異名を持つ真剣師たちが出てくるのも漫画的で楽しいところ(実際の真剣師たちも「新宿の殺し屋」とか「東海の鬼」などと呼ばれていたわけですが)。
作者の将棋への思いがひしひしと伝わってくる力作で、実在の棋士をモデルにしたキャラクターやエピソードも書かれているので、往年の将棋ファンにとっても楽しい一作だと思います。
『もの語る一手』青山美智子ほか
将棋は、決断のゲームである。無数の選択肢から、一手を選ぶ。将棋は、明快なゲームである。残酷なまでに白黒がはっきりとつく。しかし、単純な「結果」にたどり着くまでの間に、無数の思いが凝縮されている。だからこそ、将棋は物語の宝庫なのだ──。超豪華執筆陣による「決断」をテーマにした傑作将棋小説アンソロジー。
(講談社HPより引用)
『もの語る一手』は、将棋をテーマにした短編小説を集めたアンソロジーです。2024年11月号『小説現代』の特集「将棋と小説」に寄稿された短編8編が収録。執筆陣は、青山美智子、葉真中顕、白井智之、橋本長道、貴志祐介、芦沢央、綾崎隼人、奥泉光という豪華な顔ぶれです。
いずれの作品もそれぞれに魅力がありますが、個人的におすすめなのは、江戸末期から明治にかけての豪家の古文書を読み解く異色の”偽書歴史小説”「桂跳ね」(奥泉光)、情熱を失った元天才棋士・青柳と、アマ棋界で戦いつづける段というふたりの壮年男性の因縁を描く「なれなかった人」(橋本長道)、元真剣師が天才少年棋士との思い出を語る「マイチンゲールの罠」(葉真中顕)の3作です(「おまえレベルの話はしてない(大島)」(芦沢央)もおもしろいですが、これは前述の長編で読むのがおすすめ)。
非常にハイレベルなアンソロジーなので、いろいろな書き手の将棋小説を一気に読みたい方には強くおすすめいたします。
『謎々 将棋・囲碁』新井素子ほか
将棋・囲碁をテーマに描いた6つの謎。ミステリー・SF界の精鋭が集う、贅沢なアンソロジー。どれもダントツの面白さ太鼓判! この謎、解けますか?
(「BOOK」データベースより引用)
『謎々 将棋・囲碁』は、将棋と囲碁をテーマにした短編小説を集めたアンソロジーです。タイトルに「謎々」とありますが、とくにミステリに限定されているというわけではありません。全6編のうち、将棋をテーマにしているのは葉真中顕「三角文書」、深水黎一郎「▲7五歩の悲願」、瀬名秀明「負ける」の3編となっています。
なかでも個人的に好きなのは、葉真中顕「三角文書」です。舞台は、現代の文明が「超古代文明」と言われるまでになった遙か遠い未来。遺跡に保管されていた文書(=将棋の棋譜)が発見され、それが何を意味にしているのかという謎に考古学者が挑むSFなのですが、主人公の名前がヒフミーン・メイ=ジーン、彼の叔父がクニヲ・メイ=ジーン、当代随一の学者として登場する博士がハーヴ・キシン……ということで、少しでも将棋を知っている読者なら爆笑間違いなしのおバカSFとなっています。将棋と違って難しく考える必要は何もないので、ゲラゲラ笑いながら読みましょう。
まとめ
以上、おすすめの将棋小説12作の紹介でした。将棋に興味のある方におすすめしたいのはもちろんですが、どの作家も基本的には将棋を知らない人にも楽しめるように配慮して書いていると思いますので、将棋の知識がない方でも木になった作品があればぜひ手にとってみていただきたいです。
なお、以下の記事では将棋を題材にした時代小説と児童書についてそれぞれ紹介しています。よろしければあわせてお読みください。