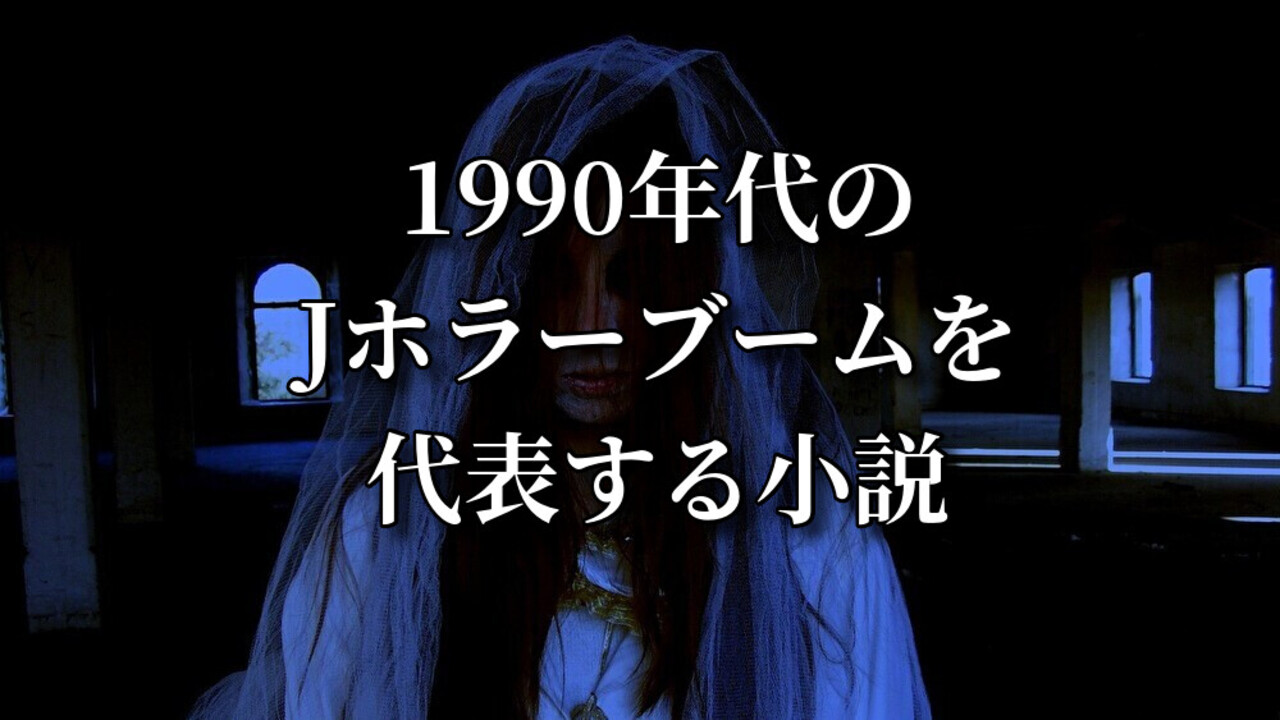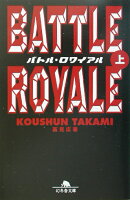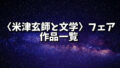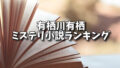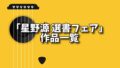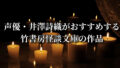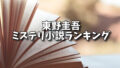2020年代に入ってから、「フェイクドキュメンタリー」「モキュメンタリー」と呼ばれる形式の物語を中心に、ホラー小説のブームが続いています。雨穴『変な家』や背筋『近畿地方のある場所について』などがその代表格でしょう。
ホラーブームといえば、1990年代に「Jホラーブーム」と呼ばれるムーブメントがありました。さまざまなホラー小説が出版され、それが映画化・テレビドラマ化などのメディアミックスによって大きな広がりを見せていました。とくに映画では世界的な人気を獲得する作品も現れたほどです。
この記事では、そんな1990年代のJホラーブームを牽引したホラー小説を紹介いたします。いずれも映画化された有名作ばかりなので、ホラー小説に詳しい方には基礎教養のようなものですが、昨今のブームでホラーに興味を持った方の参考になれば幸いです。
『リング』鈴木光司
『リング』は、1991年に刊行された鈴木光司の長編小説です。のちに続いていく「リング」シリーズの第1作目で、1998年に公開された映画版は大ヒットを記録。まさにJホラーブームを象徴する記念碑的な作品です。
映画では作中キャラクターの「貞子」のイメージがとにかく強いと思いますが、小説版は少し印象が違うかもしれません。たしかに「呪いのビデオ」による超常的な怖さも重要な要素ですが、そのビデオの謎を追っていくミステリ的な展開と、謎が紐解かれていく過程でいや増していく恐怖がポイントのように思います。個人的には映画版よりも原作のほうがより怖く、よりおもしろいです。
シリーズ作品はたくさんあるのですが、続きが読みたい方は、まず『らせん』『ループ』までの3部作を読むことをおすすめいたします。とくに『らせん』はホラー、ミステリ、SFの要素をすべて取りこんだエンタテインメントの大傑作なので、『リング』が気に入った方にはぜひ読んでいただきたいです。
『死国』坂東眞砂子
『死国』は、1993年に刊行された坂東眞砂子の長編小説です。主に童話作家として活動していた著者が初めて発表した一般向け小説で、坂東眞砂子の名を世に知らしめるきっかけとなった一作です。1999年に映画化され、『リング2』と同時上映されました。
タイトルの「死国」は「四国」とかかっており、著者の出身地でもある高知県が舞台になっています。四国八十八箇所のお遍路や当地の土俗信仰など民俗学的な要素を活かした作品で、俗にいう「因習村ホラー」の系譜にある小説です。しかし「因習村ホラー」にありがちな、田舎に対する安易な蔑視が目につく作品ではないので、「因習村ホラー」の差別的な部分が苦手な方でもご安心ください。
日本ならではの恐怖や神秘の世界を描き、 新たな伝奇と怪異を文学を生みだそうと試みる作品群を指して、「ホラー・ジャパネスク」という言葉がJホラーブームのころに使われていました。『死国』はまさにその「ホラー・ジャパネスク」の代表的な作品であり、日本のホラー小説史において重要な役割を果たした一作です。
『パラサイト・イヴ』瀬名秀明
『パラサイト・イヴ』は、1995年に刊行された瀬名秀明の長編小説です。著者のデビュー作であり、100万部を超えるベストセラーとなりました。
Jホラーブームを語るうえで外せないのが、公募新人賞の日本ホラー小説大賞です。1994年に創設され、ホラー作家の登竜門として重要な役割を果たした賞です。その審査基準は厳しく、第1回は佳作受賞作しか出ませんでしたが、第2回で見事大賞を獲得したのが『パラサイト・イヴ』でした。
人類の細胞に寄生するミトコンドリアの反乱を描くSFホラーで、当時大学院博士課程に在学していた著者の研究者としての一面が存分に活かされた一作です。どこかジメジメしたイメージのある日本のホラーのなかで、これほど理系の知識に裏打ちされた作品も珍しく、従来の国産ホラー小説のイメージを覆すような新鮮さがありました。そういう意味でも非常に画期的な作品です。
綿密なディテールでリアリティをしっかり積み重ねながら、後半にはB級ホラーのような派手なエンタテインメント性も見せてくれる、満足度の高い傑作SFホラーです。
『黒い家』貴志祐介
『黒い家』は、1997年に刊行された貴志祐介の長編小説です。第4回日本ホラー小説大賞の大賞受賞作で、同賞の先輩である『パラサイト・イヴ』と同じくミリオンセラーを記録しています。著者は『十三番目の人格 ISOLA』で第3回日本ホラー小説大賞の佳作を受賞してデビューしていますが、翌年の再チャレンジで見事大賞を射止めたということになります。
保険金殺人を扱ったサイコホラーで、超自然現象はいっさい出てきません。ホラーを巡ってはよく「幽霊より生きている人間のほうが怖い」といったことが言われますが、『黒い家』はまさに「人間が怖い」ホラーの筆頭格です。とんでもない人間と関わることになってしまった主人公の境遇に、恐怖を感じない読者はいないでしょう。
保険会社勤務の経験がある著者だけに、保険関係の描写のリアリティも抜群で、作品の質をぐっと押しあげています。間違いなくJホラーブームを代表する傑作です。
『バトル・ロワイヤル』高見広春
『バトル・ロワイヤル』は、1999年に刊行された高見広春の長編小説です。第5回日本ホラー小説大賞に投じられ、最終選考に残ったものの、中学生たちが殺し合いをするという過激な内容のために選考委員から不評を買い、受賞を逃したという曰くつきの作品。しかしそれが逆に業界内で評判を呼び、別の出版社から発売されると、落選の経緯も含めて話題となりました。
2000年に公開された映画版も、公開の規制を求める衆院議員が国会の質疑で取りあげるなど物議を醸し、それが却って作品への注目度を高めたことで大ヒットを記録。日本における「デスゲーム」ものの草分け的存在として、後世の作品に多大な影響を及ぼしました。
──と、何かと外的な部分が注目されがちな作品ではありますが、小説としては非常にまっとうな作りです。殺し合いを演じる中学生たちをしっかりと書き分けながら、彼らの恋や友情、そして生と死をエモーショナルに描きだしており、青春小説としても優れた作品となっています。タイトルは知っているけれど読んだことがない、という方はぜひ手にとってみていただきたいです。
まとめ
以上、1990年代のJホラーブームを牽引した小説の紹介でした。いずれも日本のホラー小説史に名を刻む重要な作品ばかりですので、ホラー小説初心者の方にはまず一読をおすすめいたします。