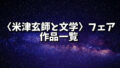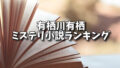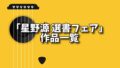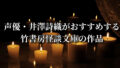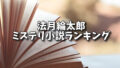この記事では、お酒にまつわるエッセイを紹介いたします。むかしからお酒をこよなく愛する作家は多く、何かしらお酒にまつわる文章を書いているケースも非常に多いです。とくに小説家という職業が現在よりずっとアウトローなイメージで、「飲む打つ買う」が男のたしなみとされた時代には、酒呑みの作家が多かったのではないかと思います。
古き良き時代から現代まで、さまざまな酒呑みたちが紡いできたエッセイを読みながらお酒を飲むのも楽しいかもしれません。
『おいしいアンソロジー ビール』阿川佐和子ほか
ビールと聞くだけで、喉がなる。幸せな気持ちになる。真夏の日本でカラカラになった体に流し込むビール。世界各国を旅して搾りたてを楽しむクラフトビール。こだわりの注ぎ方で泡まで楽しむ瓶ビール。ほろ苦い出会いから始まり、いつしか人生の友になるビール。古今東西の作家がつづった44篇の珠玉のビールアンソロジーです。
(「BOOK」データベースより引用)
『おいしいアンソロジー ビール』は、大和書房がだいわ文庫から出しているアンソロジーです。「おいしいアンソロジー」シリーズのうちのひとつで、タイトルのとおりお酒のなかでもビールにフォーカスし、さまざまな文化人のエッセイ全44編が収録されています。
収録作でもっともおもしろかったのは、夢野久作の「ビール会社征伐」。著者の新聞記者時代の話で、新聞社の面々がビールを飲むために、社会人テニスの競合が集うビール会社にテニスの試合を申しこむという爆笑の一編。面妖な怪奇小説・探偵小説の書き手というイメージの夢野久作ですが、そのイメージを完全に覆す傑作でした。
そのほか、村松友視「ビールの味と味わい」と、阿川弘之「ビール雑話」には共通の人物が登場して、おいしいビールの注ぎ方について記されているのですが、この2編を意図的に並べて収録しているところはまさにアンソロジーの妙として楽しめました。
『酒中日記』吉行淳之介編
酒の飲み方は百人百様で、それぞれの個性が出ていて興味は尽きない。酒を通じての交友、華やかな祝い酒、酒乱とその翌日の後悔の時間、大酔しての活躍状況、いくら飲んでも底なしの人物、一滴も飲めないのに雰囲気で酔っぱらってしまう人物、すこしも酔っていないようでじつは朦朧としている人物。…その他いろいろ、各種各様のタイプが揃っている。作家とお酒の珠玉エッセー61篇。
(「BOOK」データベースより引用)
『酒中日記』は、吉行淳之介編によるアンソロジーです。1963年に始まり、四半世紀以上続いた『小説現代』の名物リレー連載「酒中日記」から抜粋して、一冊にまとめたものとなっています。収録作中、いちばん古いエッセイは連載第1回目の昭和41年1月号、いちばん新しいエッセイは昭和63年2月号に掲載されたものです。
昭和の人気作家の名前がずらりと並ぶラインナップで、彼らが文壇バーを出入りしたり、銀座を飲み歩いたりしているさまは、まさにひと昔前の「作家」のイメージそのもの。当時をリアルタイムで知らなくても、今では失われたであろう業界のムードがなんだか懐かしいような気持ちになります。
作家同士の交友を垣間見る楽しさもあり、ジャンルをまたいで結構意外な交流もあったことがわかるなど、当時を知らないがゆえの発見も多くありました。お酒と文学に興味のある方にはおすすめの一冊です。続編に『また酒中日記』があります。
『酒呑みの自己弁護』山口瞳
世界の美酒・銘酒を友として三十余年、著者は常に酒と共にあった。なぜか。「酒をやめたら…もうひとつの健康を損ってしまうのだと思わないわけにはいかない」からである。酒場で起こった出来事、出会った人々を想い起こし、世態風俗の中に垣間見える、やむにやまれぬ人生の真実を優しく解き明かす。全113篇に、卓抜して飄逸な山藤章二さんのイラストが付く。
『酒呑みの自己弁護』は、山口瞳によるエッセイ集です。直木賞作家であり、「男性自身」シリーズなどのエッセイでも有名な著者が『夕刊フジ』に連載していたものをまとめた本で、全113編に及ぶ大ボリュームの一冊となっています。
戦前生まれで「戦中派」と自称する著者が、幼いころに飲んだ「はじめての酒」から戦時中の飲酒事情、サントリーの社員時代まで、さまざまな時代のお酒にまつまる出来事を軽妙かつキレのある文体で綴っています。各編の切り口も多様で、100編以上ありながら読者をけして飽きさせない、まさに名手による傑作エッセイ集といってよいでしょう。自伝的な要素もおおいに入っており、山口瞳のことをほとんど知らない読者でも、読み進むうちにどんな人物なのかわかる作りになっていため安心です。
全編にわたって山藤章二によるイラストがついており、これがまた秀逸で楽しさ倍増。酒呑みにぜひおすすめしたい一冊です。
『酒場っ子』パリッコ
安い!嬉しい!楽しい!大好き! 雑誌、WEBのお酒、酒場についての文章ではもはや欠かすことのできない、今、最も信頼のおける書き手である酒場ライター・パリッコが、これまでの酒場歩きの総決算となるエッセイ集をついに刊行! 右肩下がり時代のまったく新しいリアルな飲み歩き。どこでも楽しく飲むには。「酒場」という奥深い世界に癒しとエンターテイメントの両方を求めて通う同志の方々へ。「興味はあるけど、まだ渋い酒場に入っていく勇気がない」という方々へ。すべての呑兵衛たちへ。今夜のお酒のおともに、あるいは休肝日のおともに。
(スタンド・ブックスHPより引用)
『酒場っ子』は、パリッコによるエッセイ集です。この少し変わった筆名の著者は、酒好きが高じて2010年代ごろからお酒や酒場に関する文章をWeb等で発表するようになったという「酒場ライター」。本作はそんな著者にとって初の酒場エッセイ集となっています。
書き下ろしのエッセイが全40編収録。1編につき1店ずつ著者お気に入りの大衆酒場を紹介していくというスタイルです。基本的に東京のお店が中心で、お店とともに東京のさまざまな街についての言及も多いため、東京の地理に明るい人にはとくに楽しい本になっています。
語り口は軽く、文学的な味わいは薄いですが、個人のブログのようにスイスイ読めるので、読者が苦手な方でも手にとりやすいでしょう。おすすめのメニューや店主の人柄を楽しそうに語る文章を読んでいるうちに、無性に酒場に行きたくなること間違いなしです。
『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』村上春樹
シングル・モルトを味わうべく訪れたアイラ島。そこで授けられた「アイラ的哲学」とは? 『ユリシーズ』のごとく、奥が深いアイルランドのパブで、老人はどのようにしてタラモア・デューを飲んでいたのか? 蒸溜所をたずね、パブをはしごする。飲む、また飲む。二大聖地で出会った忘れがたきウィスキー、そして、たしかな誇りと喜びをもって生きる人々──。芳醇かつ静謐なエッセイ。
(新潮社HPより引用)
『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』は、村上春樹によるエッセイです。村上春樹が、ウイスキーの生産地として有名なスコットランドのアイラ島と、アイルランドの各地を訪ねる紀行エッセイとなっています。
文庫で100ページちょっとの薄い本で、しかも旅の写真も多く収録されているため(ちなみに写真を撮っているのは著者の奥さんです)、さらりと気軽に読める分量です。しかし分量が少なくても、村上春樹らしい流麗な文体でアイラ島の蒸留所やアイルランドのパブの空気をしっかりと味わえ、いくつもの写真がさらにイメージを喚起してくれる贅沢な一冊でもあります。
お酒にまつわるエッセイはいろいろとありますが、ウイスキーに特化したものは珍しいので、ウイスキー愛好家の方には必読の作品といっていいでしょう。
『夜の一ぱい』田辺聖子
洋酒喫茶のカクテルで味を覚えた三十代、夫との夜ごとの晩酌で酒量を上げた四十代、五十の声を聞いてすこし矛先が鈍り、八十を超えた今は、ゆっくりと夜の一杯を傾ける…。四十余年にわたる酒とのつき合いのなかでうつろいゆく、酒の好みや酒肴のこと、そして酒の上でのできごと。単行本未収録エッセイを多数収めた文庫オリジナル。
(「BOOK」データベースより引用)
『夜の一ぱい』は、田辺聖子によるエッセイ集です。昭和から平成にかけて活躍した、日本を代表する女性作家である田辺聖子。本作は、彼女が長い作家生活のなかで残したお酒にまつわるエッセイを、国文学者である浦西和彦が編纂したもので、全55編が収録されています。
収録作中いちばん古いエッセイは1966年、いちばん新しいエッセイは2004年に書かれたもの。とくに昭和の時代については、お酒にまつわる文章はどうしても男性作家のものが多いですが、そのなかで女性の視点で綴られる著者のエッセイはとても貴重です。どの作品も筆致は軽やかで、著者があっけらかんと楽しくお酒とつきあっていたことが感じられます。
女性目線であることのほかに、もうひとつの特長として、著者の生活拠点が関西にあることが挙げられます。作家がお酒を語るとなると、どうしても銀座や新宿をはじめとした東京の街に偏りがちなのですが、大阪出身で、結婚後は兵庫に居を構えていた著者は、当然のように関西を舞台にエッセイを書きます。気取りのない関西弁が飛び交うエピソードには、東京を舞台にしたものとは何か違った小気味よさがあります。
まとめ
以上、お酒にまつわるエッセイ6作の紹介でした。気になる作品のあった方はぜひ手にとっていただき、お気に入りのお酒をおともに、ページをめくってみていただければと思います。