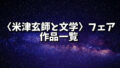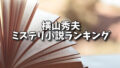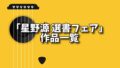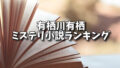日本でもっとも有名な文学賞のひとつである直木三十五賞(以下、直木賞)は、1935年に創設され、新進・中堅作家によるエンタテインメント作品の長編小説もしくは短編集を対象に、年2回発表されています。主催者は日本文学振興会ですが、これは文藝春秋社が設立した団体なので、実質的には文藝春秋社が運営している賞といってよいでしょう。
そんな直木賞に対抗すべく、1988年に新潮社が創設した文学賞が山本周五郎賞(以下、山本賞)です。明文化されているわけではありませんが、こちらも新進・中堅作家によるエンタテインメント作品が主な対象で、受賞作・候補作の傾向も直木賞に近いものがあります。
山本賞受賞作家がのちに直木賞を獲ることは多く(その逆はありません)、同じ作品が両賞にノミネートされることもよくありますが、ダブル受賞を果たすケースは意外と少ないです。山本賞が創設された1988年以降で、わずかに3例しかありません。
本記事では、その稀有な偉業を達成した3つの小説を紹介いたします。
『邂逅の森』熊谷達也
・第17回(2004年)山本周五郎賞受賞
・第131回(2004年上半期)直木三十五賞受賞
秋田の貧しい小作農に生まれた富治は、伝統のマタギを生業とし、獣を狩る喜びを知るが、地主の一人娘と恋に落ち、村を追われる。鉱山で働くものの山と狩猟への思いは断ち切れず、再びマタギとして生きる。失われつつある日本の風土を克明に描いて、直木賞、山本周五郎賞を史上初めてダブル受賞した感動巨編!
(文藝春秋BOOKSより引用)
2004年に史上初めて直木賞・山本賞のダブル受賞を達成したのが、熊谷達也の『邂逅の森』です。大正から昭和の秋田県を舞台に、マタギとして生きる松橋富治の波瀾万丈の人生を綴った大河小説の傑作です。
マタギとは、東北や北海道などの山間部に住み、狩猟を生業とする猟師の集団のこと。独自の厳しい掟やしきたりを守り、山々の恵みを糧に生きるマタギについて著者はじつに綿密に取材し、彼らの暮らしぶりを生き生きとリアルに描いています。小さな山村で慎ましくも力強く生きる富治らの息遣いが、まるですぐそばから聞こえてくるようです。
人間はいかに自然と対峙するかという大きなテーマを軸に、名士の娘との身分違いの恋や、マタギとは異なる鉱山夫の暮らし、戦争を背景に移り変わっていく社会情勢など、さまざまな要素が盛りこまれているのも本書の魅力となっています。
また、富治以外の脇役たちもみなそれぞれに個性的で、物語を大いに盛りあげてくれます。なかでも印象深いのは、富治の運命に大きく関わる2人の女性、文枝とイクでしょう。マタギの世界は当然のように男性が中心ですが、彼女たちの生き様をしっかり描くことで、物語にいっそうの厚みと深みが与えられています。
長さは文庫で500ページ超。多くの読者にとってなじみの薄いマタギが題材ということもあって、手を出しにくいと感じられる方もいるかもしれませんが、いったん読みはじめればリアリティとリーダビリティを兼ね備えた文章で、どっぷりとマタギの世界に浸れることでしょう。ダブル受賞も納得の感動巨編です。
『テスカトリポカ』佐藤究
・第34回(2021年)山本周五郎賞受賞
・第165回(2021年上半期)直木三十五賞受賞
メキシコのカルテルに君臨した麻薬密売人のバルミロ・カサソラは、潜伏先のジャカルタで日本人の臓器ブローカーと出会う。二人は新たな臓器ビジネスを実現させるため日本へ向かった。川崎で生まれ育った天涯孤独の少年・土方コシモは、バルミロに見いだされ、彼らの犯罪に巻きこまれていく。海を越えて交錯する運命の背後に、滅亡した王国の恐るべき神の影がちらつく─。人間は暴力から逃れられるのか。第165回直木賞受賞作。
(「BOOK」データベースより引用)
2021年、『邂逅の森』以来17年ぶりに直木賞と山本賞のダブル受賞を果たしたのが、佐藤究の『テスカトリポカ』です。両賞だけでなく、その年の各種ミステリランキングでも軒並み上位にランクインした超弩級の犯罪小説です。
中核をなすキャラクターはふたり。ひとりは、メキシコの麻薬カルテル「ロス・カサソラス」の幹部、バルミロ・カサソラです。残虐極まりないやり口で勢力を拡大してきた「ロス・カサソラス」は、対立組織との抗争の末に壊滅の危機に陥り、バルミロは単身インドネシアへ逃げ延びます。いつか資金と戦力を得て復讐を成し遂げようと誓うバルミロは、ジャカルタで出会った日本人ブローカー・末永と手を組み、臓器売買ビジネスを始めるため日本へ赴きます。
日本にはもうひとりの主要人物、メキシコから川崎に逃れてきた母と、暴力団員の父のあいだに生まれた少年・土方コシモがいます。育児放棄され、学校にもなじめない彼は13歳のときにある事件を起こして少年院へ。その後17歳で出院後すると、木工技術の腕を買われてある工房で働くことになります。
やがてコシモはバルミロと出会い、巨大で邪悪なビジネスに巻きこまれていきます。資本主義の残酷さの権化ともいえる麻薬ビジネス、臓器売買ビジネスを圧倒的なスケールで描き、裏社会で生きる人間たちの容赦のない暴力性を迫真のリアリティであぶり出す──そんな目を背けたくなるような、それでいて目が離せなくなるような血と暴力の世界を描く暗黒小説、それが『テスカトリポカ』です。
また、アステカ時代のメキシコに伝わるアステカ神話も本作の非常に重要な要素となっています。そもそもタイトルにもなっている「テスカトリポカ」とは、アステカ神話における最強の神のこと。バルミロは亡き祖母の影響でこの古代の神を信仰しており、彼の行動原理において大きなウエイトを占めています。
血なまぐさい現代の凶悪犯罪を描きながらも、滅亡したアステカ王国の神の姿が終始ちらつくことで、物語は常にどこか魔術的・幻想的な雰囲気を帯びています。これも通常の犯罪小説にはない『テスカトリポカ』の大きな魅力といえるでしょう。
山本賞では選考委員から絶賛され、満場一致の受賞。直木賞では、主に男性選考委員が残酷な描写に嫌悪感を抱いたことで激論になったものの、女性選考委員が熱烈に支持したことで受賞に至りました。たしかに人を選ぶ部分もあるかもしれませんが、他では味わえない圧倒的な迫力に満ちた傑作であり、直木賞受賞もきわめて妥当だと思います。
『木挽町のあだ討ち』永井紗耶子
・第36回(2023年)山本周五郎賞受賞
・第169回(2023年上半期)直木三十五賞受賞
ある雪の降る夜に芝居小屋のすぐそばで、美しい若衆・菊之助による仇討ちがみごとに成し遂げられた。父親を殺めた下男を斬り、その血まみれの首を高くかかげた快挙は多くの人々から賞賛された。二年の後、菊之助の縁者という侍が仇討ちの顛末を知りたいと、芝居小屋を訪れるが──。現代人の心を揺さぶり勇気づける令和の革命的傑作誕生!
(新潮社公式HPより引用)
永井紗耶子の『木挽町のあだ討ち』が直木賞・山本賞をダブル受賞したのは2023年。『テスカトリポカ』以来2年ぶりということで、非常に短いスパンで史上3作目の快挙達成となりました。
『木挽町のあだ討ち』は江戸時代、文化・文政年間(1804~30年)を舞台にした時代小説です。木挽町の芝居小屋のすぐそばで起きた仇討ちについて知りたいという若侍が、芝居小屋にまつわる人々に話を聞いて回るという筋立てで、各章ごとにさまざまな立場の語り手が登場します。
時代小説に苦手意識のある方も多いかもしれませんが、本書では聞き手となる若侍が江戸の町人文化に疎い設定で、第1章の語り手である木戸芸者(芝居小屋の門前で客の呼びこみを行う芸人)が、舞台となる芝居小屋の世界について説明してくれるため、読者もそれにしたがってすんなりと物語のなかへ入っていけるように工夫がなされています。文章も読みやすいですし、時代小説が苦手な人でもかなりとっつきやすいはずです。
仇討ちの真相に迫るというミステリ的な構成を用いながら、社会のはみ出し者である芝居小屋の人々の粋と人情を描き、女性や弱い立場に置かれた人々へ目配せもしっかりとあって、現代的な時代小説の傑作に仕上がっていると思います。
どちらの選考会でも受賞に否定的な委員はほぼおらず、満場一致といっていい評価を獲得。時代小説ファン以外にもおすすめできる、万人向けのエンタテインメント小説だと思います。
まとめ
以上、山本周五郎賞と直木三十五賞とダブル受賞している小説、3作品の紹介でした。いずれもダブル受賞にふさわしい小説だと思いますので、気になった方はぜひ読んでみていただければと思います。