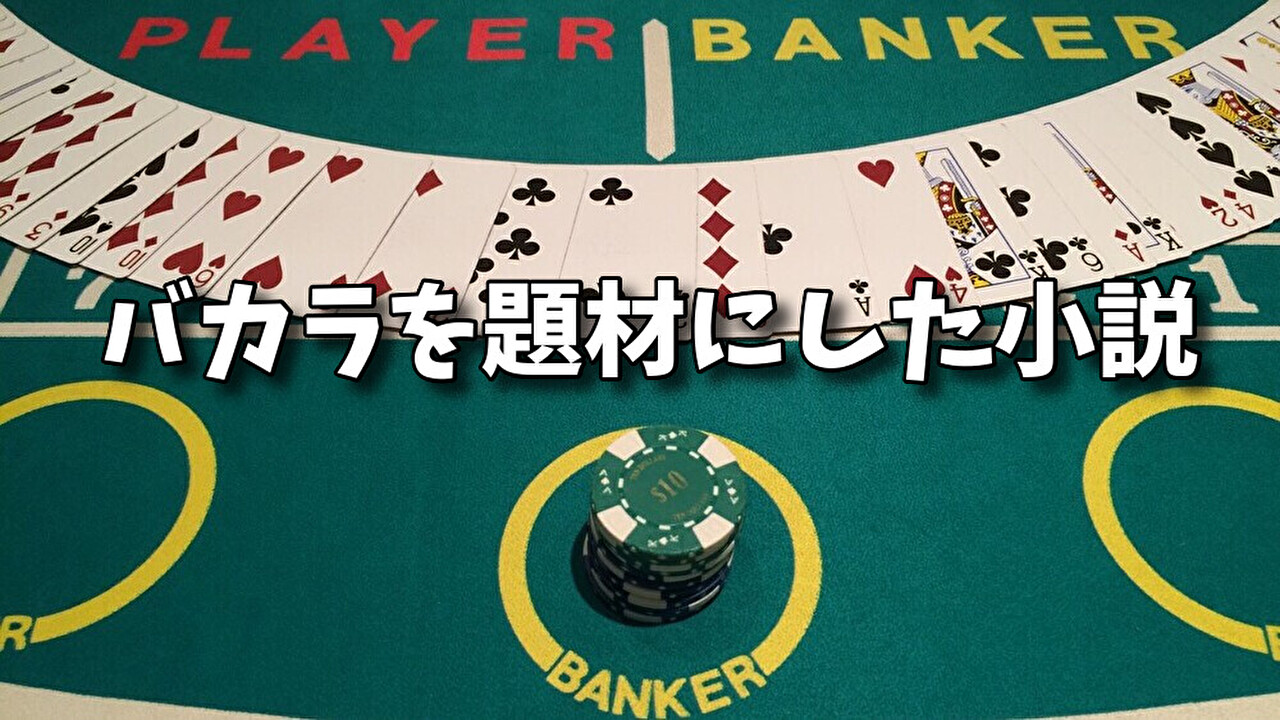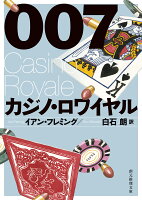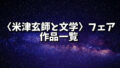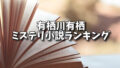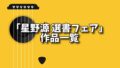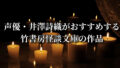バカラは、しばしば「カジノの王様」と呼ばれるトランプを用いたゲームで、配られたカードの数によって「バンカー」と「プレイヤー」のどちらが勝つかを予想して賭けます。ルールがシンプルで、決着がスピーディー、そして高額の賭けになりやすいところがカジノの王様と呼ばれるゆえんでしょう。
この記事では、そんなバカラを題材にしたギャンブル小説について紹介いたします。
『波の音が消えるまで』沢木耕太郎
サーフィンの夢を諦め、バリ島から香港を経由し、流木のようにマカオに流れ着いた伊津航平。そこで青年を待ち受けていたのはカジノの王「バカラ」だった。失った何かを手繰り寄せるようにバカラにのめり込んでいく航平。偶然の勝ちは必要ない、絶対の勝ちを手に入れるんだ──。同じくバカラの魔力に魅入られた老人・劉の言葉に導かれ、青年の運命は静かに、しかし激しく動き出すのだった。
(新潮社HPより引用)
『波の音が消えるまで』は、沢木耕太郎による長編小説です。紀行ノンフィクションの名作『深夜特急』でも手に汗握るギャンブル描写を見せてくれた沢木耕太郎が、フィクションでバカラを描いた大傑作が本書です。
サーファーとしての夢を諦めた主人公が、ひょんなことからマカオのカジノでバカラにとり憑かれ、必勝法を求めて闘いつづけるギャンブル小説。バカラのルールも作中で丁寧に説明されるため、知識がなくても読むのに支障はありません。シンプルなゲームであるバカラの何がそんなに魅力なのか、そしてバカラに必勝法はあるのか。文庫3冊の大長編で、カジノの王様の魔力をたっぷりと読ませてくれます。
脇役たちも個性的でそれぞれに魅力があり、彼らと主人公の人生が交錯する青春小説としてもすばらしい出来です。おそらくこれを超えるバカラ小説はそう出てこないでしょう。
『新麻雀放浪記 申年生まれのフレンズ』阿佐田哲也
かつて“坊や哲”などと恐れられ、バクチ稼業に明け暮れていた私もすっかり中年男になって、ハラはふくれ、頭も禿げ上り、誰も昔の雄姿を信じてくれぬ。そんな私がふとしたはずみで入った留置場でバクチ好きの学生に出会った。それがきっかけで、私にも往年の闘志が甦ってきた。麻雀、サイホンビキ、牌ホンビキと、この申年生まれの相棒と日本各地にマカオにと遠征。嵐のようなツキ、私は人生を賭けた大勝負に出た……。人はなぜギャンブルをやるのか──その心理をいきいきととらえた娯楽長篇。
(Amazonより引用)
『新麻雀放浪記 申年生まれのフレンズ』は、阿佐田哲也による長編小説です。ギャンブル小説の金字塔『麻雀放浪記』の後日談で、博奕から足を洗ってすっかり中年になった坊や哲が登場します。
『麻雀放浪記』は娯楽小説の頂点といってもいいくらいすごい作品なので、それと比較するのはちょっと酷ですが、本作は煮え切らない中年の悲哀が色濃く描かれることもあり、前作ほどのエンタテインメント性はありません。しかし物語の終盤、マカオのカジノを舞台に描かれるバカラの大勝負は、さすが阿佐田哲也と思わせてくれる迫力があります。
『麻雀放浪記』とはまた別の味わいのあるギャンブル小説としておすすめいたします。
『ジゴクラク』森巣博
赤坂の非合法賭場。博奕を生業とする「わたし」は、バカラの魔力に取り憑かれた美少女、舞ちゃんと知り合う。毎夜10万円を溶かし続けた彼女の負けは、1000万円に達した。少女を「喰い」まくったのは「わたし」だったのだ。舞ちゃんの体を張った願いから、二人は共同戦線を張ることになる。乾坤一擲の大勝負が始まった──。 賭博の真髄を突く警句の数々。史上最強のギャンブル小説!
(Amazon商品紹介ページより引用)
『ジゴクラク』は、森巣博による長編小説です。著者は海外を拠点に生活するプロのギャンブラーで、ギャンブルに関する本を多数執筆。ギャンブルの種目ではとくに牌九とバカラに精通しているようで、本書もそうした著者の経験が存分に活かされた作品です。
ただ、正直気になる部分も多い小説ではあります。とくに、著者自身がモデルと思われる40代の中年男が18歳の美少女と恋愛をし、しかも品のないポルノのような描写が多い点は読んでいてかなりしんどいです。全体を通して軽薄で蛇足の多い文章も、著者の持ち味といえばそうなのですが、魅力的な個性とは言いがたいと思います。
とはいえ、ギャンブルに関する数々の警句はさすがプロ。「勝ち逃げだけが博奕の極意」「博奕には根拠などいらない。確信だけがあればいい」と言い切る小気味よさは読ませるものがあります。阿佐田哲也とはまた違うプロのギャンブラーによる物語を読みたい人は、手にとってみてもいいかもしれません。
『百家楽餓鬼』吉田修一(『犯罪小説集』所収)
田園に続く一本道が分かれるY字路で、一人の少女が消息を絶った。犯人は不明のまま十年の時が過ぎ、少女の祖父の五郎や直前まで一緒にいた紡は罪悪感を抱えたままだった。だが、当初から疑われていた無職の男・豪士の存在が関係者たちを徐々に狂わせていく……。(「青田Y字路」)痴情、ギャンブル、過疎の閉鎖空間、豪奢な生活……幸せな生活を願う人々が陥穽に落ちた瞬間の叫びとは? 人間の真実を炙り出す小説集。
(KADOKAWAHPより引用)
「百家楽餓鬼」は、吉田修一による短編小説です。タイトルは「ばからがき」と読みます。実際の事件をモデルにした作品を集めた短編集『犯罪小説集』に収録されています。「百家楽餓鬼」のモデルになっているのは大王製紙事件。元取締役会長の井川意高が、グループ会社の資金・総額約106億円をカジノで遊ぶために不正に引き出し、特別背任罪で逮捕されたという事件です。
創業家の御曹司(本作では製紙業ではなく運輸業)がバカラにハマるという点も実際の事件と同じですが、主人公を単なる「お金持ちのバカ息子」というイメージで描いていないところが本作の魅力です。普通の子ども・若者だった時代のことや、御曹司ゆえの孤独、NGO活動で貧困に喘ぐ子どもたちを救済しようする姿などを多面的に描くことで、ギャンブルに溺れて墜ちていくさまがよりシリアスに感じられる作りになっています。
そして何より印象的なのはラストシーンでしょう。正気と狂気、善と悪、生と死の狭間を彷徨うような混沌を描きながら、同時にどこかに突き抜けていくような強烈なインパクトをもらたす描写は忘れがたいものがあります。
『007/カジノ・ロワイヤル』イアン・フレミング
“イギリスが誇る秘密情報部で、ある常識はずれの計画がもちあがった。ソ連の重要なスパイで、フランス共産党系労組の大物ル・シッフルを打倒せよ。彼は党の資金を使いこみ、高額のギャンブルで一挙に挽回しようとしていた。それを阻止し破滅させるために送りこまれたのは、冷酷な殺人をも厭(いと)わない007のコードをもつ男──ジェームズ・ボンド。007初登場作を新訳でリニューアル!”
(東京創元社HPより引用)
『007/カジノ・ロワイヤル』は、イアン・フレミングによる長編小説です。世界でいちばん有名なスパイ、ジェームズ・ボンドが初登場する「007」シリーズの1作目。2006年の映画版ではポーカーによる対決が描かれていましたが、原作で登場するのはバカラです。
組織の資金を使いこみギャンブルで取り返そうとするソ連のスパイを相手に、ボンドがカジノで勝負に挑むというストーリーで、とてつもない金額を賭けた大勝負はまさに手に汗握るおもしろさ。カジノのシーンは物語の半分ほどで終わってしまい、後半は王道的なスパイ・アクションものになりますが、ギャンブル小説として一読の価値はあると思います。
『バカラの勝負』モーリス・ルブラン(『バーネット探偵社』所収)
パリのどまん中で私立探偵社を開業したバーネットは、実はルパンだった。難事件を次つぎに解明していくユーモア探偵小説。
(偕成社HPより引用)
「バカラの勝負」は、モーリス・ルブランによる短編小説です。「アルセーヌ・ルパン」シリーズのひとつで、ルパンが探偵ジム・バーネットとして活躍する連作短編集『バーネット探偵社』に収録されています。
社交場でバカラに興じていたひとりの男性が、ゲームが終わって参加者が帰ったあとに殴り殺されるという事件が発生。バーネットは懇意の刑事の依頼を受けて捜査を開始し、後日事件当日の様子を完全再現するために、ふたたび「バカラの勝負」が始まる──というのがあらすじです。
小説としてはあくまでミステリで、バカラというゲームを詳細に描くストーリーではありませんが、バーネットが容疑者たちを心理的に追いこんでいく様子が楽しい洒脱な一編です。ちなみに、森元サトルによる漫画版『mystery classics ~甦る名探偵達~ アルセーヌ・ルパン編(1)』 では、バカラの展開を原作より具体的に描いているので、こちらもおすすめです。
まとめ
以上、バカラを題材にしたおすすめのギャンブル小説6作の紹介でした。どれも趣向がバラバラなので、好みに合いそうな作品から手にとってみていただければと思います。