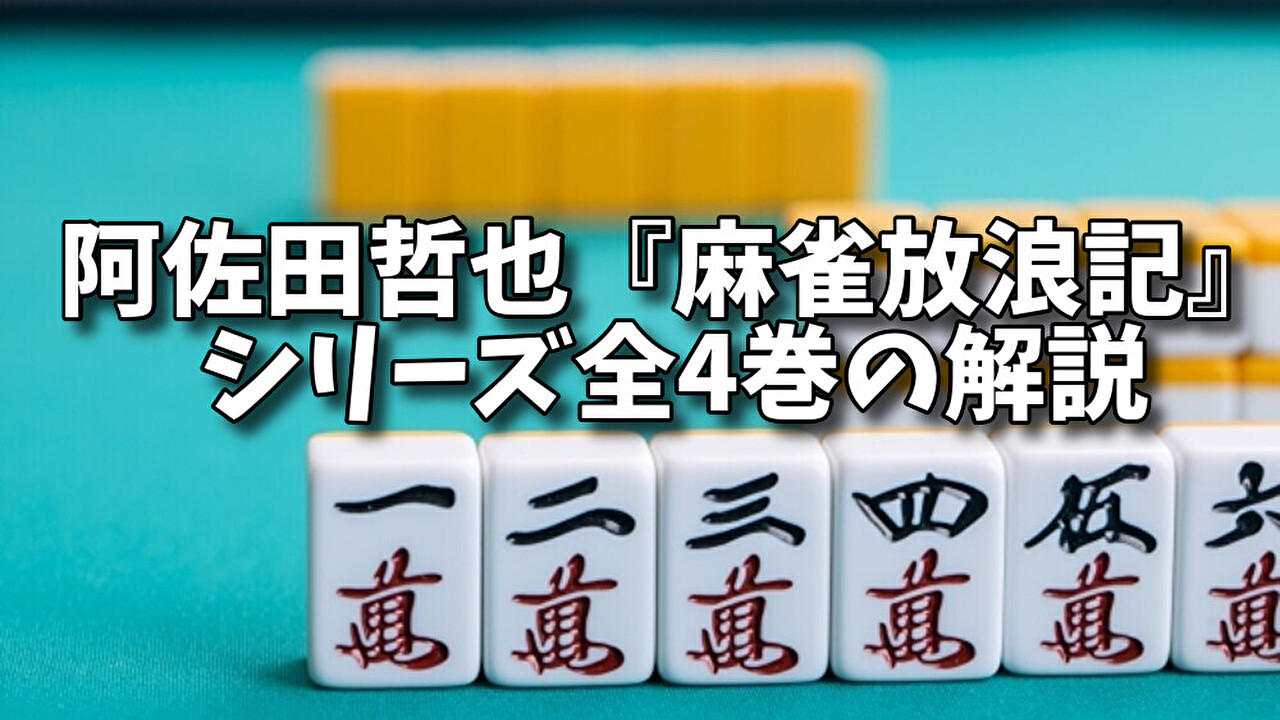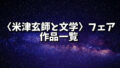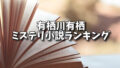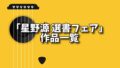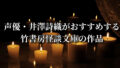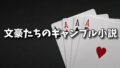阿佐田哲也による小説『麻雀放浪記』は、麻雀小説の原点にして頂点というべき金字塔的作品であり、またピカレスクロマンの大傑作でもあります。エンタテインメント小説としてとにかくおもしろいので、麻雀好きであろうとそうでなかろうと、おもしろい小説が読みたいという人には強くおすすめします。人によっては、人生で最高の読書体験になる──そんな可能性すらあると個人的には思っています。
『麻雀放浪記』はシリーズで全4巻あります。「青春編」から始まり、「風雲編」「激闘編」までの3作でいったん完結し、そのほかに「番外編」が1作という構成です。
文庫本は角川文庫、文春文庫、双葉文庫から刊行されています。このなかでは双葉文庫がいちばん新しく、文字が大きくて読みやすいのでおすすめです。4巻とも書評家・北上次郎氏の熱い解説付きです。
この記事ではシリーズ全4巻について紹介し、あらすじや感想を書いていきます。この大傑作シリーズを手にとるきっかけになれば幸いです。なお、あらすじの引用元はすべて双葉社公式HPです。
『麻雀放浪記(1)青春編』
敗戦直後、焦土と化した東京で、全てを失った“坊や哲”。戦中の勤労動員で知り合った“上州虎”と再開し、博打世界へ入り込んでいく。チンチロ博打の賭場で出会った“ドサ健”や、凄腕のバイニン“出目徳”との出会いを通じて、麻雀打ちとして生きることになった坊や哲。麻雀に生きる男たちを描くピカレスクロマンの大傑作。
第1巻の「青春編」では、主人公の“私”こと“坊や哲”が、敗戦直後の東京で博打の世界に入りこんでいくとこから描かれていきます。冒頭は麻雀ではなくチンチロリンのシーンから始まりますが、薄汚れた賭場に浮浪者じみた男たちが集まっている様子からすでに何かが起きそうな期待感に満ちています。猥雑で、無秩序で、いかがわしく、それゆえに尋常ではないエネルギーが渦巻く時代の雰囲気を感じられるのも『麻雀放浪記』の楽しいところでしょう。
16歳にして麻雀に生きる道に飛びこんだ坊や哲。彼を取り巻く脇役たちも一筋縄ではいかない曲者ばかりです。最大のライバルというべきバイニン(麻雀を生業とするプロ)・ドサ健、坊や哲にイカサマ技のノウハウをたたき込むオックスクラブのママ、隻腕の傷痍軍人でベテランのバイニンである上州虎など、印象深いあだ名ともに次々へと魅力的な脇役が登場します。そんな強烈な個性あふれる面々と麻雀卓を囲むことになるわけですから、肝心の対局シーンがつまらないわけがありません。
もちろんキャラクターの魅力だけではなく、賭け麻雀に挑む心の裡を描いた心理小説としても抜群におもしろく、ヒリヒリと手に汗を握りながらページをめくることになります。とくに本作の最後を飾る坊や哲、ドサ健、女衒の達、出目徳の4人による対局は圧巻のひと言。麻雀に生きるしかない男たちの、文字どおり命をかけた戦いに興奮しない読者はいないでしょう。最後の一文がまたシビれるほどかっこいいので、ぜひ実際に読んでいただきたいと思います。
『麻雀放浪記(2)風雲編』
出目徳が死んでから数年後、坊や哲はヒロポン地獄に落ちていた。ヒロポン欲しさに打った麻雀で粗相を働いた坊や哲は、新たな賭場を求めて東京を出ることに。旅の途中で知り合った坊主のクソ丸と少女ドテ子と博打列車で大阪へ向かう。関西を舞台に“ブウ麻雀”で麻雀の鬼たちと鎬を削る、傑作シリーズ第2弾。
第2巻「風雲編」の舞台は昭和26年ごろ。「青春編」は昭和20年から始まるので、そこから数えると6年ほど経っていることになります。冒頭からいきなり坊や哲がヒロポン中毒になっていて驚きますが、その後坊や哲は訳あって関西へ博打修行の旅へ出発します。
まず、関西へ向かう夜行列車のなかからすでにおもしろいのがすごいところ。博打列車といって、貸元が一両丸ごと貸し切って賭場にしてしまうという、じつにわくわくする舞台が用意されているのです。ここで行われるのは麻雀ではなく「アトサキ」という博打ですが、「青春編」のチンチロリンがそうだったように、麻雀以外のギャンブルも扱われるのが『麻雀放浪記』の魅力のひとつでしょう。
クソ丸、ドテ子といった脇役を加えて、坊や哲はまず大阪に乗りこみ、関西を発祥とする「ブウ麻雀」でライバルたちとしのぎを削ります。その後、神戸・京都と舞台を移していきますが、京都の博打寺・大恩寺で住職らと闘う寺麻雀がとにかく圧巻。プロの麻雀打ちが次々寺に殴りこみをかけ、和尚や坊主たちと死闘を繰り広げるド派手な闘いで、外連味たっぷりのおもしろさはシリーズ中でも断トツです。
「青春編」のドサ健らと比較すると、「風雲編」の脇役たちは正直少しばかり魅力が落ちる気がするのですが、大恩寺での激闘はそんな小さな不満を帳消しにして余りあります。個人的にはシリーズ全4巻のなかでも1巻と2巻がとくにおすすめなので、1巻がおもしろかった方には続けて2巻も読んでいただけるとうれしいです。
『麻雀放浪記(3)激闘編』
戦争の爪痕が消えつつある東京で、変わらず博打漬けの日々を送る坊や哲。しかし、麻雀の打ち過ぎからか、右肘に故障が出て、いかさまができなくなってしまった。そんなある日、太いカモの話を聞き、地下組織のTS会から1日1割の烏金を借りて勝負に挑むが……。出目徳やドサ健とも違う近代化された麻雀打ちたちと戦う、大傑作ピカレスクロマンの第3弾。
第3巻「激闘編」は、「青春編」「風雲編」と続いてきた坊や哲の物語の完結編です。まだ第4巻の「番外編」がありますが、こちらはその名のとおり番外なので、シリーズはここでいったん完結といって間違いはないと思います。
「風雲編」からさらに1年ほど時が経ち、日本が敗戦から復興を遂げつつある時代。東京の街がどんどん小綺麗になっていき、かつて溢れるほどいた浮浪者の姿もめっきり減った──「激闘編」はそんな社会の変化を背景とした作品です。
社会の急速な変化とともに、博打打ちを取り巻く状況も当然変わっています。麻雀が大衆化し、ネクタイを締めたサラリーマンたちもそれなりの腕を持つようになり、本業で稼いだお金で博打を打つ。そんな博打だけに生きているわけではない博打打ちが増え、生粋のバイニンである坊や哲やドサ健のようなタイプの人間にとってはずいぶん肩身の狭い時代になってしまっているのです。
対局シーンにおいても「青春編」「風雲編」のような痛快さは影を潜め、どこか煮え切らないムードが常に漂っています。だからといって、「激闘編」がつまらない小説だというわけではありません。時代に合わなくなってしまった坊や哲の怒りや苦渋が描かれ、そのことでかえって博打打ちとしての彼の生き様が深みをもって浮かび上がってくる──過去2作にはない、そんな独自の魅力が「激闘編」には備わっています。
そして、なんといっても胸を打たれるのがラストシーン(『麻雀放浪記』はどの巻もそうですが)。内容についてここでは触れませんが、放浪の果てにたどり着いた坊や哲の結末をぜひ見届けていただきたいです。
『麻雀放浪記(4)番外編』
戦後も安定期に入ったが、坊や哲は唐辛子中毒で身体を壊してしまった。博打稼業から足を洗って、勤め人として平穏な日々を送っていたある日、会社の同僚が一人の男を連れてくる。その男の名はドサ健。そして坊や哲は、健や北九州で出会った李億春たちと再び麻雀の深淵へ……。現代ピカレスクロマンの金字塔、堂々の完結編!
「番外編」の舞台は昭和30年ごろ。日本経済がますますめざましい成長を見せようという時代、坊や哲はすでにプロの博打打ちであることをやめ、会社勤めをしています。そんな坊や哲に代わって本作の主人公を務めるのは、北九州の雀荘で働いている青年・李億春。会社の出張で北九州へ来た坊や哲が、ふらっと立ち寄った雀荘で李と出会うところから物語は始まります。
親指を除いた両手の指をすべて詰め、いつも黒い手袋をしている李は、この時代にあってもギャンブルに命を賭けることを厭わない生粋の博打打ち。強い相手と打ちたいという純粋さとエネルギーに満ちた李は、シリーズ中でも屈指の無軌道さを持つキャラクターかもしれません。
李は坊や哲との再戦を求めて東京へ向かいますが、その途中大阪で打った麻雀がきっかけで、陳徳儀という男の手先となります。陳は大阪で人気のブウ麻雀を東京でも流行らせて、東京の雀荘を乗っ取る計画を立てている男で、いわば本作の悪役です。そんな陳らを迎え撃つのは、シリーズを読んできたファンにはおなじみのドサ健。
「P」という雀荘を巡って彼らがしのぎを削るバトルが本作のハイライトで、「番外編」であろうが対局シーンのおもしろさは衰えません。そして毎度のことながら、そのあとに待っているラストが今回もやはりすばらしいです。
シリーズ全体のなかでは「番外編」は若干完成度に落ちるところがありますが、それはほかの巻がおもしろすぎるからであって、「番外編」もすぐれたエンタテインメント小説であることは間違いありません。
まとめ
以上、『麻雀放浪記』シリーズ全4巻の紹介でした。戦後の娯楽小説を代表する本当におもしろい作品なので、少しでも興味を持った方にはぜひ読んでいただきたいです。
ほかにもスピンオフ作品の『ドサ健ばくち地獄』や、中年になった坊や哲が主人公の『新麻雀放浪記 申年生まれのフレンズ』などもありますし(続編とはいえ、だいぶ趣が変わっていますが)、『麻雀放浪記』を原作・原案とする漫画や映画もそれぞれ複数あります。今回紹介した全4巻を読み終えても、『麻雀放浪記』の世界はまだまだ広がりを見せているので、そちらに足を踏み入れるのも楽しいと思います。