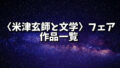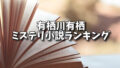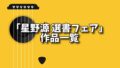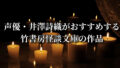SFやミステリ、あるいは純文学まで幅広く執筆し、いずれにおいても高い評価を獲得している作家・宮内悠介。日本SF大賞、吉川英治文学新人賞、三島由紀夫賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞、日本推理作家協会賞など文学賞もジャンルを問わず多数受賞しており、ノミネートまで含めればその幅はさらに広がります。
そんな宮内悠介が作品の題材にしばしば選んでいるのが盤上遊戯(ボードゲーム)。デビュー短編の「盤上の敵」で取りあげた囲碁を中心に、さまざまな種目を扱って物語の世界に落しこんでいます。どれも本当に高水準の作品ばかりで、ボードゲームの小説を描かせたら彼の右に出る者はいないと個人的には思っています。
そこでこの記事では、宮内悠介によるボードゲーム小説を紹介していきます。
『盤上の夜』
彼女は四肢を失い、囲碁盤を感覚器とするようになった──。若き女流棋士の栄光をつづり、第1回創元SF短編賞で山田正紀賞を贈られた表題作にはじまり、同じジャーナリストを語り手にして紡がれる、盤上遊戯、卓上遊戯をめぐる6つの奇蹟。囲碁、チェッカー、麻雀、古代チェス、将棋……対局の果てに人知を超えたものが現出する。デビュー作品集ながら直木賞候補となり、日本SF大賞を受賞した、2010年代を牽引する新しい波。
(東京創元社HPより引用)
『盤上の夜』は、2012年に刊行された宮内悠介のデビュー連作短編集です。表題作「盤上の夜」は第1回創元SF短編賞の応募作で、山田正紀賞(選考委員特別賞)を受賞。単行本として上梓された『盤上の夜』は第33回日本SF大賞を受賞し、さらに第147回直木賞の候補にもなりました。毎年恒例の『SFが読みたい!』ランキングでも国内編の2位にランクイン。デビュー作にして圧倒的な評価を獲得した珠玉の作品集です。
全6編収録で、すべて伝統的なボードゲームを題材にした小説となっています。具体的には、「盤上の夜」では囲碁、「人間の王」ではチェッカー、「清められた卓」では麻雀、「象を飛ばした王子」ではチャトランガ、「千年の虚空」では将棋、最後の「原爆の局」ではふたたび囲碁が取りあげられています。
どの作品もゲームそのものの魅力とSF的な奇想・発想が結びつき、それらを通じて人類や世界についての哲学的な思索を読者に促すような深みがあって、きわめてハイレベルな短編集だと思います。難しい理系の知識が求められるわけではないので、SFになじみのない読者もご安心ください。6編すべておもしろいですが、個人的には6編のなかで唯一対局シーンがたっぷり描写される麻雀小説「清められた卓」がおすすめです。麻雀については著者自身がプロ級の腕前ということもあってか、かなり気合いの入った超一級の作品です。
『月と太陽の盤 碁盤師・吉井利仙の事件簿』
放浪の碁盤師・吉井利仙が、かつて棋士だったころの打ち回しに魅せられ、彼を先生と呼んで追いかけている若手囲碁棋士の愼。姉弟子の衣川蛍衣も巻き込みながら、囲碁を巡る数々の事件に遭遇し、棋士としても成長していく。コンゲームあり、サスペンスあり、異なる味わいを持つ物語を重ね、囲碁という宇宙に魅入られた人間を描ききった傑作ミステリ登場!
(光文社HPより引用)
『月と太陽の盤 碁盤師・吉井利仙の事件簿』は、2016年に刊行された連作短編集で、宮内悠介にとっては初のミステリです。登場するゲームは「盤上の夜」「原爆の局」に続いて囲碁。宮内悠介は「盤上の夜」を書いたモチベーションとして、「囲碁はものすごくおもしろいゲームなのでどうか知ってくれ」という気持ちがあったと語っており、囲碁は非常に思い入れのあるゲームのようです。
といっても、本作では囲碁の対局シーン自体は出てきません。ワトスン役の愼は若手のプロ棋士ですが、ホームズ役を務めるのは囲碁の盤を作る職人(=碁盤師)である吉井利仙で、囲碁というより碁盤を巡る連作ミステリとなっています。囲碁のルールがまったくわからなくても問題ありません。
連作という形式でありながら一編ごとに趣向が異なっているのが本書の特徴のひとつで、コンゲーム風であったり心理ミステリであったり、それぞれに味わいがありますが、いちばんの力作は表題作「月と太陽の盤」でしょう。建物の図面が出てくる本格ミステリで、綾辻行人などのいわゆる「新本格ミステリ」を愛読していたという著者の一端が伺える一編となっています。
『エターナル・レガシー』(『超動く家にて』所収)
雑誌『トランジスタ技術』のページを“圧縮”する架空競技を描いた「トランジスタ技術の圧縮」、ヴァン・ダインの二十則が支配する世界で殺人を目論む男の話「法則」など16編。日本SF大賞、吉川英治文学新人賞、三島由紀夫賞、星雲賞を受賞し、直木・芥川両賞の候補となった著者の傑作快作怪作を揃えた自選短編集。あとがき、文庫版オリジナルのおまけも収録。
(東京創元社HPより引用)
「エターナル・レガシー」は、2018年に刊行された短編集『超動く家にて』に収録されている短編小説です。これもまた囲碁が題材で、プロ棋士が主人公のお話です。古式ゆかしい8ビットのマイクロプロセッサー・Z80の化身(?)を名乗るおじさんが主人公の元に訪ねてくるというギャグのような導入で始まり、AIがプロを凌駕する時代における棋士の存在意義を問う物語が展開されます。
囲碁の愛好家というだけでなく、元プログラマーという経歴を持つ宮内悠介だからこそ書ける感動的な傑作短編です。
『星間野球』(『超動く家にて』所収)
「星間野球」は、先述の「エターナル・レガシー」と同じく『超動く家にて』に収録されている短編小説です。題材となるボードゲームは野球盤。当然ふたりのプレイヤーが野球盤で戦うストーリーなのですが、なんとその舞台が宇宙ステーションで、そこから地球へ帰還する権利を賭けて争うという爆笑必至の一編となっています。
バカバカしい設定ですが、頭脳だけでなくフィジカルも使い、宇宙ステーションならではの荒技も飛びだすバトルは意外にも(?)白熱し、白熱すればするほどバカバカしさが増すという非常に愉快なSFです。
『最後の役』(『国歌を作った男』所収)
お昼どきに家に侵入(!?)して、その家の冷蔵庫の食材で美味しい料理を作る(!?)犯人を追うコミカルミステリー短編。(「料理魔事件」)「ピーガー」というSNSが存在した、一九六五年の日本。開高健を待ち受けていた、世界初の炎上事件の謎を紐解いた先に待っていた真実に迫るSF短編。(「パニックー一九六五年のSNS」)植物状態となった囲碁の名人と祖父と、最新テクノロジーで碁の対局をする少女。いつか再び目を覚ましてくれると信じて。(「十九路の地図」)など、色とりどりの読後感を持つ13篇を収録!
(「BOOK」データベースより引用)
「最後の役」は、2024年に刊行された短編集『国歌を作った男』に収録されている掌編小説(ショートショート)です。タイトルから察せられるとおり、題材になっているゲームは麻雀。小説というよりエッセイ風の作品で、作者によると「内容はおおむね事実」とのこと。考えごとをしているときなどに麻雀の役をつぶやく、という自身の癖について綴るショートストーリーです。
『十九路の地図』(『国歌を作った男』、『謎々 将棋・囲碁』所収)
将棋・囲碁をテーマに描いた6つのミステリー。この謎解けますか? 囲碁盤に頭を打ち、救急車で運ばれた主婦。ぬいぐるみが原因を探るユーモアミステリー(「碁盤事件」)。超古代文明の遺跡に保管されていた文書から、将棋というゲームと神の存在を説く考古学者・ヒフミーン(「三角文書」)。不登校の中学生が、植物状態の祖父と脳インタフェースを使って碁を打っていたところ奇跡が(「十九路の地図」)。全ての駒を最低一度は動かさなくてはならない──特殊ルールの上に繰り広げられる不思議なゲームとは?(「7五歩の悲願」)。両親を亡くした少女が、囲碁の先生である“おばあちゃん”と同居することになって……(「黒いすずらん」)。将棋で「投了できる人工知能」を開発する若者たち(「負ける」)。
(角川春樹事務所HPより引用)
「十九路の地図」は、先述の短編集『国歌を作った男』に収録されている短編小説です。これもまた囲碁を扱ったお話です。もともとは将棋と囲碁がテーマの小説を集めたアンソロジー『謎々 将棋・囲碁』のために書かれたものなので、ほかの将棋小説・囲碁小説も読みたいという方は、そちらで読むのがよいかと思います。
アンソロジーのタイトルに「謎々」とあることからミステリの作品集と思う人も多いと思いますが、「十九路の地図」はミステリではなくSFです。植物状態になってしまった元本因坊タイトル保持者の祖父と、ブレイン・マシン・インタフェースを通じて囲碁を打つ孫娘の物語。「エターナル・レガシー」とはまた違った形で、囲碁とテクノロジーをかけ合わせた秀作です。憎めない祖父のキャラクターも楽しい一編。
おまけ
ボードゲームとは違いますが、宮内悠介はギャンブルを扱った小説も書いており、ゲーム的な駆け引きが楽しめるジャンルとして近い部分があるので、おまけとして2作紹介します。
ひとつは、宇宙を舞台にした借金取りSFという斬新な設定の連作短編集『スペース金融道』のなかに収録されている「スペース蜃気楼」。カジノ宇宙船でのポーカーを題材にしており、なおかつ経済小説としても優れた一編です。
そしてもうひとつは、中編の『黄色い夜』。賭博を主要産業する国が舞台で、国盗りをもくろむ主人公が砂漠にそびえるカジノ・タワーに乗りこみ、各階で次々とギャンブル対決に挑んでいく物語です。さまざまなゲームが描かれ、ダンジョンRPGを攻略していくような楽しさがある傑作です。
まとめ
以上、宮内悠介によるボードゲーム小説(およびおまけのギャンブル小説)の紹介でした。何を書かせても水準以上のすばらしい作家だと思っているので、少しでも気になった作品があればぜひ手にとっていただきたいです。