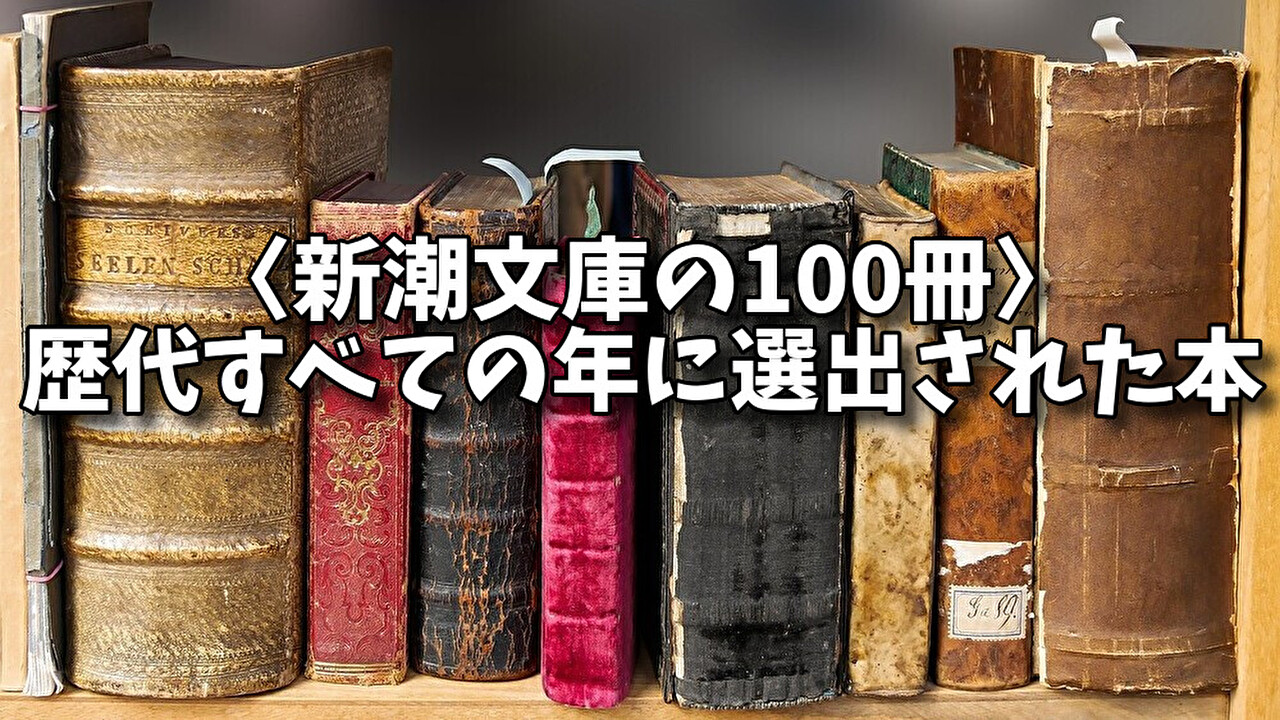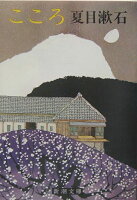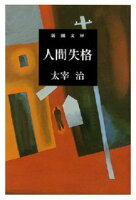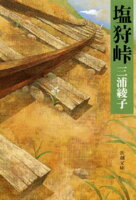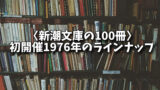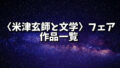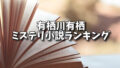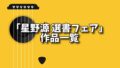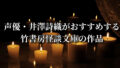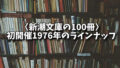新潮社が毎年夏におこなっている恒例のフェア、「新潮文庫の100冊」。1976年に始まり、現在(2025年)までに全50回開催されています。100冊のラインナップは毎年入れ替わりますが、一方で50年間すべての年に選出されている小説が10作あります。
本記事ではその選ばれし10作について紹介いたします。最初に日本の文学作品、次に海外の文学作品を挙げていきます。あらすじの引用元はすべて新潮社HPです。
なお、ラインナップを調べるために以下のサイトを参考にさせていただきました。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%AE%E6%96%87%E5%BA%AB%E3%81%AE100%E5%86%8A
https://www.shinchosha.co.jp/nami/tachiyomi/20240627.html
https://technopolis2719.sakura.ne.jp/9810sin.htm
『こころ』夏目漱石
鎌倉の海岸で、学生だった私は一人の男性と出会った。不思議な魅力を持つその人は、“先生”と呼んで慕う私になかなか心を開いてくれず、謎のような言葉で惑わせる。やがてある日、私のもとに分厚い手紙が届いたとき、先生はもはやこの世の人ではなかった。遺された手紙から明らかになる先生の人生の悲劇──それは親友とともに一人の女性に恋をしたときから始まったのだった。
『こころ』は、1914年に発表された夏目漱石の長編小説。近代人のエゴイズムの苦悩と絶望を描いた作品です。歴代の「新潮文庫の100冊」において、夏目漱石の小説は『吾輩は猫である』『坊っちゃん』『三四郎』『それから』などもよく選ばれており、同じ年に最大4作が選出されたこともあります。しかしそんな数ある名作のなかでも、もっとも代表作と呼ぶにふさわしいのはやはり『こころ』でしょう。
新潮文庫の累計発行部数において第1位といわれており、その部数は750万部以上。もちろんその部数は毎年増えています。刊行から100年以上経っても読まれつづけている永遠の名作です。
『新編 銀河鉄道の夜』宮沢賢治
貧しく孤独な少年ジョバンニが、親友カムパネルラと銀河鉄道に乗って美しく哀しい夜空の旅をする、永遠の未完成の傑作である表題作や、「よだかの星」「オツベルと象」「セロ弾きのゴーシュ」など、イーハトーヴォの絢爛にして切なく多彩な世界に、「北守将軍と三人兄弟の医者」「饑餓陣営」「ビジテリアン大祭」を加えた14編を収録。賢治童話の豊饒な醍醐味をあますところなく披露する。
『新編 銀河鉄道の夜』は、1934年に刊行された表題作など全14編を収録した宮沢賢治の作品集。『銀河鉄道の夜』は第1次稿から第4次稿まで内容の異なるバージョンがあり、現在の新潮文庫『新編 銀河鉄道の夜』に収録されているのは第4次稿となります。
「新潮文庫の100冊」初年度である1976年当時の新潮文庫版が第何次稿だったのかまでは調べがついていませんが、現在の『新編 銀河鉄道の夜』が発売されたのは1989年で、表題作のほかに収録されている短編のラインナップは当時と違っているものと思われます。
いずれにしても、表題作の『銀河鉄道の夜』が歴代すべての年に選出されてきたことは間違いありません。いまなお様々な解釈を呼ぶ、切なく美しい永遠の童話です。
『人間失格』太宰治
「恥の多い生涯を送って来ました」。そんな身もふたもない告白から男の手記は始まる。男は自分を偽り、ひとを欺き、取り返しようのない過ちを犯し、「失格」の判定を自らにくだす。でも、男が不在になると、彼を懐かしんで、ある女性は語るのだ。「とても素直で、よく気がきいて(中略)神様みたいないい子でした」と。ひとがひととして、ひとと生きる意味を問う、太宰治、捨て身の問題作。
『人間失格』は、1948年に発表された太宰治の中編小説。太宰治といえばやはりこの作品を思い浮かべる人が多いでしょう。人間の孤独、葛藤、絶望を描いた自伝的小説で、いわば太宰の遺書のような作品です。実際、『人間失格』脱稿の1か月後に太宰は死去し、完結した小説としては本作が最後となっています(本作のあとに書かれた『グッド・バイ』は未完)。
新潮文庫の累計発行部数は、前述の夏目漱石『こころ』に次ぐ第2位です。
『黒い雨』井伏鱒二
一瞬の閃光に街は焼けくずれ、放射能の雨のなかを人々はさまよい歩く。原爆の広島──罪なき市民が負わねばならなかった未曾有の惨事を直視し、“黒い雨”にうたれただけで原爆病に蝕まれてゆく姪との忍苦と不安の日常を、無言のいたわりで包みながら、悲劇の実相を人間性の問題として鮮やかに描く。被爆という世紀の体験を、日常の暮らしの中に文学として定着させた記念碑的名作。
『黒い雨』は、1966年に刊行された井伏鱒二の長編小説。広島出身の著者が原爆の悲劇を綴った作品で、旧小畠村の被爆者・重松静馬さんの日誌を参考にして執筆されました。タイトルの「黒い雨」とは、原爆投下後に降った放射性物質を含んだ雨のことを指します。
井伏鱒二の代表作といえば『山椒魚』『さざなみ軍記・ジョン万次郎漂流記』などが新潮文庫に入っていますが、意外にも「新潮文庫の100冊」に選出されたことがあるのは『黒い雨』のみとなっています。
『塩狩峠』三浦綾子
結納のため、札幌に向った鉄道職員永野信夫の乗った列車は、塩狩峠の頂上にさしかかった時、突然客車が離れて暴走し始めた。声もなく恐怖に怯える乗客。信夫は飛びつくようにハンドブレーキに手をかけた……。明治末年、北海道旭川の塩狩峠で、自らを犠牲にして大勢の乗客の命を救った一青年の、愛と信仰に貫かれた生涯を描き、生きることの意味を問う長編小説。
『塩狩峠』は、1968年に刊行された三浦綾子の長編小説。三浦綾子の代表作といえば、ベストセラーになった『氷点』を思い浮かべる方が多いと思いますが、『氷点』は角川文庫からのみ発売されており、新潮文庫には入っていません。また、前述の4名以外にも近代文学の名だたる文豪がいるなか、三浦綾子がこのラインナップに入ってくるのは少し意外に感じられるかもしれません。
しかし『塩狩峠』も累計発行部数300万部を超えるベストセラーであり、今なお読み継がれる三浦綾子の代表作のひとつであることは間違いありません。1909年に実際に起きた鉄道事故で殉職した男性をモデルに、著者の重要なテーマであるキリスト教の愛と信仰を描いた名作です。
『罪と罰』フョードル・ドストエフスキー
鋭敏な頭脳をもつ貧しい大学生ラスコーリニコフは、一つの微細な罪悪は百の善行に償われるという理論のもとに、強欲非道な高利貸の老婆を殺害し、その財産を有効に転用しようと企てるが、偶然その場に来合せたその妹まで殺してしまう。この予期しなかった第二の殺人が、ラスコーリニコフの心に重くのしかかり、彼は罪の意識におびえるみじめな自分を発見しなければならなかった。
『罪と罰』は、1866年に発表されたフョードル・ドストエフスキー(ロシア)の長編小説。ドストエフスキーの代表作というだけでなく、世界のあらゆる小説のなかでも最高峰の一作といっていいでしょう。老婆殺害の罪を犯したラスコーリニコフの贖罪と救済を描いた名作です。
ドストエフスキーといえば『罪と罰』と双璧をなす長編に『カラマーゾフの兄弟』があり、新潮文庫に収録されていますが、こちらは意外にも「新潮文庫の100冊」には一度も選出されていません。これほどの作品であれば2作同時の選出があってもいいように思いますが、『罪と罰』が優先されつづけてきたようです。
『車輪の下』ヘルマン・ヘッセ
ひたむきな自然児であるだけに傷つきやすい少年ハンスは、周囲の人々の期待にこたえようとひたすら勉強にうちこみ、神学校の入学試験に通った。だが、そこでの生活は少年の心を踏みにじる規則ずくめなものだった。少年らしい反抗に駆りたてられた彼は、学校を去って見習い工として出なおそうとする……。子どもの心と生活とを自らの文学のふるさととするヘッセの代表的自伝小説。
『車輪の下』は、1905年に発表されたヘルマン・ヘッセ(ドイツ)の長編小説。多感で繊細な優等生ハンスの孤独と苦しみを描いた青春小説で、ヘッセの自伝的小説といわれています。
少し古い統計ですが、1972年から1982年までの10年間の『車輪の下』の売上を比較すると、日本では本国ドイツの10倍もよく読まれているそうです(光文社古典新訳文庫『車輪の下で』「解説」より)。規律の厳しい神学校でハンスが感じる抑圧は、この国で学校教育を受ける人々にとくに共感されるのかもしれません。
『変身』フランツ・カフカ
ある朝、気がかりな夢から目をさますと、自分が一匹の巨大な虫に変わっているのを発見する男グレーゴル・ザムザ。なぜ、こんな異常な事態になってしまったのか……。謎は究明されぬまま、ふだんと変わらない、ありふれた日常がすぎていく。事実のみを冷静につたえる、まるでレポートのような文体が読者に与えた衝撃は、様ざまな解釈を呼び起こした。海外文学最高傑作のひとつ。
『変身』は、1915年に発表されたフランツ・カフカ(ドイツ)の中編小説。主人公のグレーゴル・ザムザがある朝、突然巨大な毒虫になってしまうという冒頭があまりに有名な不条理小説の代表的作品です。
何の説明もなく、元の姿に戻ることもできず、ただ毒虫として日常を過ごすしかない――なんとも理不尽な話ですが、描写されている主人公の様子を逐一想像してみると思わず笑ってしまうようなところもあります。実際、カフカはこれをコメディとして書いたという説もあるそうです。さまざまな解釈が可能なことも傑作である証拠のひとつでしょう。
『異邦人』アルベール・カミュ
母の死の翌日海水浴に行き、女と関係を結び、映画をみて笑いころげ、友人の女出入りに関係して人を殺害し、動機について「太陽のせい」と答える。判決は死刑であったが、自分は幸福であると確信し、処刑の日に大勢の見物人が憎悪の叫びをあげて迎えてくれることだけを望む。通常の論理的な一貫性が失われている男ムルソーを主人公に、理性や人間性の不合理を追求したカミュの代表作。
『異邦人』は、1942年に発表されたアルベール・カミュ(フランス)の中編小説。カフカと並ぶ不条理小説の代表的作家であるカミュの小説家デビュー作です。不条理小説という共通項とは無関係ですが、こちらも「きょう、ママンが死んだ」という書き出しが非常に有名な一作です。
新潮文庫の累計発行部数では第5位。海外文学のなかでは次に紹介する『老人と海』に次ぐ第2位です。ちなみにカミュといえば新型コロナウイルスの影響で再び注目された『ペスト』も有名ですが、こちらは「新潮文庫の100冊」には一度も選出されたことがありません。
『老人と海』アーネスト・ヘミングウェイ
八十四日間の不漁に見舞われた老漁師は、自らを慕う少年に見送られ、ひとり小舟で海へ出た。やがてその釣綱に、大物の手応えが。見たこともない巨大カジキとの死闘を繰り広げた老人に、海はさらなる試練を課すのだが──。自然の脅威と峻厳さに翻弄されながらも、決して屈することのない人間の精神を円熟の筆で描き切る。著者にノーベル文学賞をもたらした文学的到達点にして、永遠の傑作。
『老人と海』は、1952年に発表されたアーネスト・ヘミングウェイ(アメリカ)の中編小説。老漁師と巨大なカジキとの死闘を克明に描いた代表作で、ヘミングウェイはこの作品によってピューリッツァー賞とノーベル文学賞を受賞しました。1961年にヘミングウェイは亡くなりますが、『老人と海』は生前に刊行された最後の作品となります。
新潮文庫の累計発行部数では第3位、海外文学のなかでは堂々の第1位となっています。現在の新潮文庫版は2020年に発売された新訳版なので読みやすく、サブテキストも充実しているのでおすすめです。
まとめ
以上、「新潮文庫の100冊」において歴代すべての年に選出された10作品の紹介でした。いずれも歴史の試練に耐えてきた名作ばかりです。一読してみれば、長きにわたって読まれてきた理由の一端を知ることができるかもしれません。
なお、1976年に「新潮文庫の100冊」が初めて開催された際の作品の一覧を以下の記事でまとめています。もしよろしければあわせてチェックしてみてください。