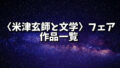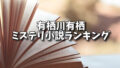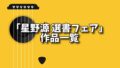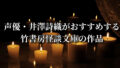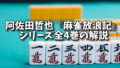ギャンブル好きの作家はむかしから多く、歴史に名を残す小説家がギャンブルにまつわる文章を書いている例もたくさんあります。なかには手のつけられないギャンブル狂の作家もいたりして、偉大な文豪が博打に振り回されているエピソードにはなんとも言えないおかしみがあります。
賭博の歴史は紀元前まで遡れるほど古く、当然文学作品のなかでもさまざまな形で描かれてきました。そこでこの記事では、偉大な文豪たちの書いたギャンブル小説について紹介いたします(「文豪」に明確な定義はありませんが、概ね「近代文学の大家」という程度に思っていただければと思います)。
『スペードの女王』アレクサンドル・プーシキン(『スペードの女王・ベールキン物語』所収)
西欧文学を貪欲に摂取し、自家薬籠中のものとし、近代ロシア文学の基礎をうち立てたロシアの国民詩人プーシキン(1799―1837)。「駅長」など5篇の短篇から成り、ロシア散文小説の出発点となった『ベールキン物語』。簡潔明快な描写で、現実と幻想の交錯を完璧に構築してみせた『スペードの女王』。本書は名訳者と謳われた神西清の訳筆に成る、プーシキン傑作短篇集である。
(岩波書店HPより引用)
「スペードの女王」は、「ロシア近代文学の父」ともいわれる詩人・作家のアレクサンドル・プーシキンによる短編小説です。登場する種目は、18世紀から19世紀にかけて欧米で流行したファロ(ファラオ)というトランプゲーム。
若い工兵士官のゲルマンは、ある老伯爵夫人がファロで必ず勝つ秘訣を知っているという話を聞き、その秘技を調べるため彼女の被後見人であるリーザを誘惑します。やがてゲルマンは首尾よく伯爵夫人に近づくことに成功しますが……というあらすじで、賭博を通じて人間のエゴや野心を描きだした逸品です。次に紹介するドストエフスキーも大絶賛したことで知られています。
『賭博者』フョードル・ドストエフスキー
ドイツのある観光地に滞在する将軍家の家庭教師をしながら、ルーレットの魅力にとりつかれ身を滅ぼしてゆく青年を通して、ロシア人に特有な病的性格を浮彫りにする。ドストエフスキーは、本書に描かれたのとほぼ同一の体験をしており、己れ自身の体験に裏打ちされた叙述は、人間の深層心理を鋭く照射し、ドストエフスキーの全著作の中でも特異な位置を占める作品である。
(新潮社HPより引用)
『賭博者』は、ロシアの文豪フョードル・ドストエフスキーの長編小説です。世界的な大文豪であるドストエフスキーですが、じつはひどいギャンブル依存症で、多額の借金を抱えていたことでも知られています。出版社に借金の肩代わりをしてもらうかわりに、規定のページ以上の作品を納品しないといけない契約を結び、その納期ギリギリに口述筆記で書きあげられたのが『賭博者』です。
本作で描かれるのは、カジノにおけるルーレット賭博。ドストエフスキー自身の体験をもとに、ギャンブルによって破滅していく青年の姿が描かれます。わずかな時間にとんでもない金額が飛び交うさまはスリリングで恐ろしいものですが、ドストエフスキー特有のエキセントリックなキャラクター描写のせいか、どこか狂気的な喜劇のようにも見えます。
『富籤』アントン・チェーホフ(『カシタンカ・ねむい 他七篇』所収)
日本におけるチェーホフを考えるとき、神西清(1903-1957)の名を抜きにしては語れない。短篇の名手の逸品を翻訳の名手が手がけた9篇、これに訳者のチェーホフ論2篇を加えた〈神西清のチェーホフ〉とも言うべきアンソロジー。表題作の他に、「アリアドナ」「かき」「少年たち」等を収録。
(岩波書店HPより引用)
「富籤」は、ロシアを代表する劇作家で、小説家でもあるアントン・チェーホフの短編小説です。タイトルの「富籤」とは、日本で一般的に言われている「宝くじ」のこと。1887年に発表された作品で、そんなにむかしから宝くじがあるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、富籤はじつ紀元前まで遡ることのできる歴史あるギャンブルなのです。
10ページほどの短い作品で、筋は非常にシンプル。妻の買った富籤の番号が、新聞で発表されている当たり番号と途中まで一致していることに気づいた夫婦は、続きの番号を確かめる前に、もし当たっていたらそのお金で何をしようと想像を膨らせます。それぞれ好き勝手に妄想を広げていくと、段々と相手のことや親族のことが憎らしくなってきて……というお話です。
ユーモアと風刺はチェーホフの特徴ですが、この作品は残酷なブラックユーモアが光る逸品。青空文庫でも読めますが、紙なら『カシタンカ・ねむい 他七篇』(岩波文庫)で読むことができます。
『木馬の勝ち馬』D・H・ロレンス(『ロレンス短編集』所収)
ロレンスは大胆かつ露骨な性表現と精妙な心理描写で、1920年代から広く人気を博した。狂人となったかつての恋人と再会した妻を問い詰める夫…「薔薇園の影」、いつまでも帰らぬ夫を怒りながら待つ妻…「菊の香」、ちょっとしたことから、健全な選択の可能性に気付く乙女…「二番手がいちばん」等、これぞロレンスという世界を一冊に凝縮した精選の13短編。懇切丁寧な作品解説・年譜・訳注付。
(新潮社HPより引用)
「木馬の勝ち馬」は、『チャタレイ夫人の恋人』で有名なD・H・ロレンスの短編小説です。邦題は訳によって「木馬を駆る少年」「木馬に乗った少年」「木馬の勝者」などいくつかありますが、本記事では新潮文庫『ロレンス短編集』をベースとしています。
本作で取りあげられているギャンブルは競馬です。中流家庭でありながら社会的対面を保つにはもっと金が必要だと考えている母親。その声ならぬ声を敏感に察する息子のポール少年は、おもちゃの木馬を駆ると不思議なお告げが聞こえ、競馬の勝ち馬を的中させることができる力を手にします。家のいたるところから聞こえてくる「もっとお金がなくちゃ!」とささやきをかき消すため、少年は狂気にとりつかれたように木馬を駆り……というあらすじです。
ギャンブルの恐ろしさではなく、母親の金銭への執着と、それが原因で親子の関係を歪んでしまっている恐怖こそが、この小説の主眼でしょう。幼い少年が狂気に駆り立てられるさまが哀しい寓話的な一編です。
『勝負事』菊池寛(『ちくま日本文学027 菊池寛』所収)
「涙の谷」に住む生活者に 一条の光明を与える物語
解説:井上ひさし 接続詞「ところが」による菊池寛小伝
勝負事/三浦右衛門の最後/忠直卿行状記/藤十郎の恋/入れ札/ある抗議書/島原心中/恩讐の彼方に/仇討三態/仇討禁止令/新今昔物語より(弁財天の使 好色成道)/好色物語より(大力物語 女強盗)/屋上の狂人/父帰る/話の屑籠/私の日常道徳
(Amazonより引用)
「勝負事」は、小説家・劇作家であり、文藝春秋社創立、芥川賞・直木賞創設の立役者でもある菊池寛の掌編小説です。菊池寛といえば大のギャンブル好きで有名で、「ギャンブルは絶対使っちゃいけない金に手につけてからが本当の勝負だ」という危うい名言(?)でも知られていますが、じつはこの発言の出典は明確ではなく、実際にそのようなことを言っていたのかは定かではありません。いずれにしても麻雀や競馬などに熱中していたことは事実のようです。
「勝負事」はかつて賭博に溺れていた祖父と、その孫のささやかなエピソードを綴った物語。数ページの短いストーリーですが、最後の一行にぐっとくる佳品です。青空文庫でも読めますが、紙で読みたい方は『ちくま日本文学027 菊池寛』(ちくま文庫)でどうぞ。
『モンテカルロの下着』久生十蘭(『十蘭レトリカ』所収)
十蘭の前に十蘭なく、十蘭の後に十蘭なし。破天荒へ向けての完璧な計算、予想を裏切り期待を裏切らないウルトラC。最高の達成度を示す異色の傑作群。「胃下垂症と鯨」「モンテカルロの下着」「ブゥレ=シャノアヌ事件」「フランス感れたり」「心理の谷」「三界万霊塔」「花賊魚」「亜墨利加討」の圧巻八篇。
(「BOOK」データベースより引用)
「モンテカルロの下着」は、「小説の魔術師」とも称された久生十蘭による短編小説です。日本からパリに留学中の貧しい女学生ふたりが、ルーレットの必勝法がわかったといって意気揚々とモンテカルロのカジノへ乗りこむユーモラスな一編。流麗でありながらどこかとぼけた筆致が、独特の笑いを誘う楽しいギャンブル小説です。
久生十蘭自身、演劇研究のためパリに留学していた際に、モンテカルロまで足を伸ばしてルーレットに励んでいたそう。本作と同じくルーレットを題材にした短編に「黒い手帳」があります。
『競馬』織田作之助(『世相・競馬』、『ちくま日本文学035 織田作之助』所収)
終戦直後の大阪の混沌たる姿に、自らの心情を重ねた代表作「世相」、横紙破りの棋風で異彩を放つ大阪方棋士・坂田三吉の人間に迫る「聴雨」、嫉妬から競馬におぼれる律儀で小心な男を描いた「競馬」、敬愛する武田麟太郎を追悼した「四月馬鹿」等、小説8篇に、大阪人の気質を追究した評論「大阪論」を併録。自由な精神で大阪の街と人を活写した織田作之助の代表作集。
(講談社HPより引用)
「競馬」は、太宰治や坂口安吾らとともに無頼派、新戯作派と呼ばれた作家、織田作之助による短編小説です。そのものずばりのタイトルですが、著者本人もやはり競馬を好んでいたようで、冒頭から競馬場における群集心理がリアリティたっぷりに描かれています。
主人公は死んだ妻「一代」の名前にちなんで1番の馬を買いつづける男・寺田。妻と関係があったらしい男への嫉妬からいつのまにか競馬に溺れていき、最後のあり金をすべて注ぎこむレースまで、短い紙数で波瀾万丈のストーリーが楽しめます。
青空文庫でも読めますが、紙で読みたい方は『世相・競馬』(講談社文芸文庫)や、『ちくま日本文学035 織田作之助』(ちくま文庫)でどうぞ。
まとめ
以上、文豪たちの書いたギャンブル小説のおすすめ7選でした。むかしから変わらないギャンブルが魔力をぜひこれらの作品で味わっていただければと思います。