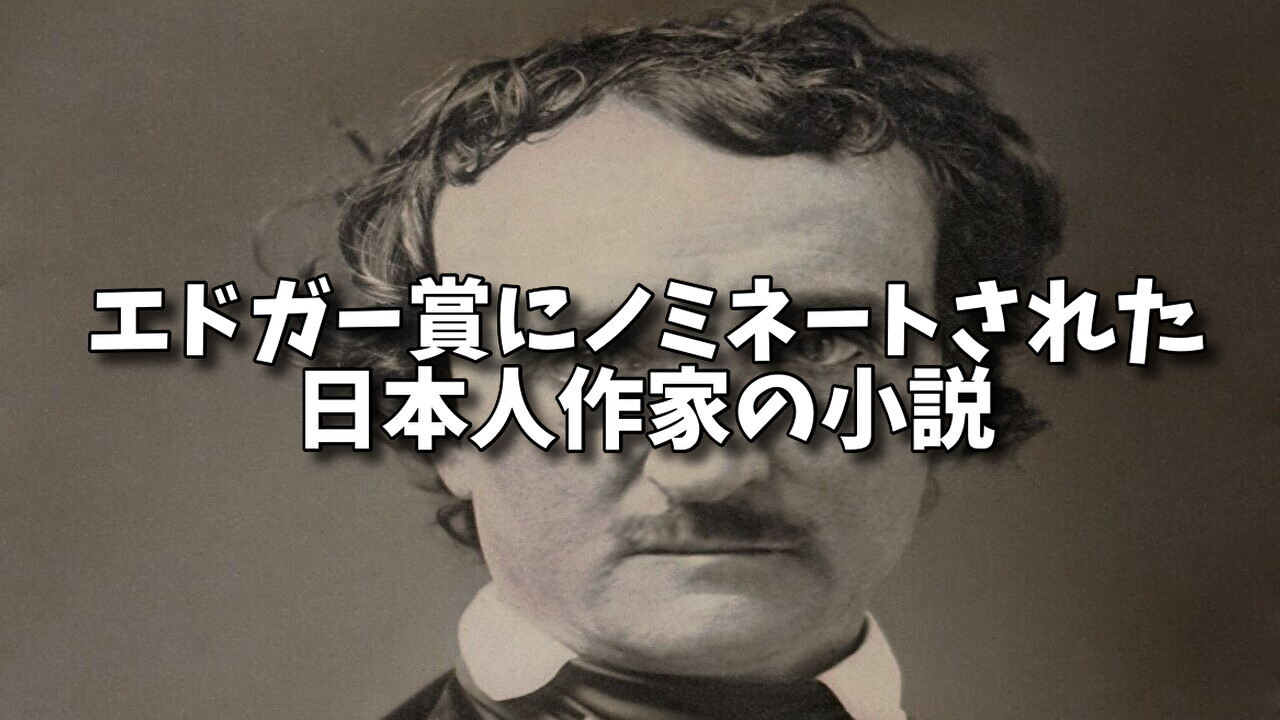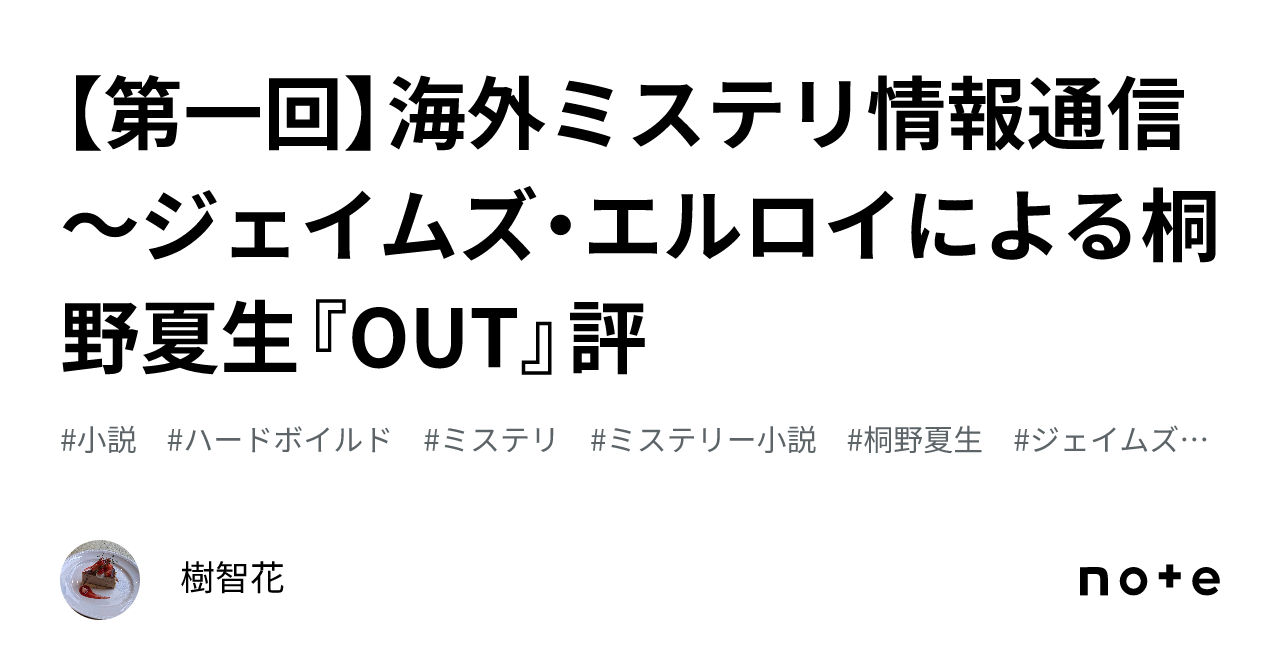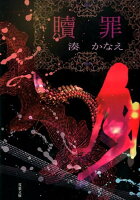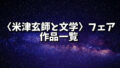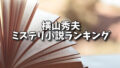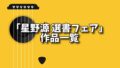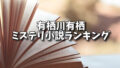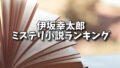エドガー・アラン・ポー賞、通称・エドガー賞は、アメリカ探偵作家クラブが主催する文学賞です。ミステリ分野の作品を対象とした賞で、名前の由来はもちろん、世界初の推理小説「モルグ街の殺人」の作者であるエドガー・アラン・ポーです。アメリカ探偵作家クラブ(Mystery Writers of America)のアルファベットの頭文字をとって、MVA賞と呼ばれることもあります。
エドガー賞はアメリカのミステリ界でもっとも権威のある賞といわれており、当然受賞作はアメリカ人作家の作品が多いですが、翻訳作品にも門戸が開かれています。いずれも受賞には至っていないものの、日本人作家の作品の英訳版が最終候補にノミネートされたこともあります。
そこでこの記事では、エドガー賞の最終候補にノミネートされた日本人作家の小説3作について紹介いたします。
『OUT』桐野夏生
深夜の弁当工場で働く主婦たちは、それぞれの胸の内に得体の知れない不安と失望を抱えていた。「こんな暮らしから抜け出したい」そう心中で叫ぶ彼女たちの生活を外へ導いたのは、思いもよらぬ事件だった。なぜ彼女たちは、パート仲間が殺した夫の死体をバラバラにして捨てたのか? 犯罪小説の到達点!
(講談社HPより引用)
『OUT』は、桐野夏生による長編小説です。日本では1997年に単行本が発売され、第51回日本推理作家協会賞を受賞。アメリカでハードカバーが刊行されたのは2003年で、翌2004年にエドガー賞最優秀長編賞に日本人作家として初めてノミネートされました。
深夜の弁当工場で働く主婦たちが、パート仲間が殺した夫の遺体処理に手を貸したことを機に日常から逸脱していく(まさに“アウト”していく)に姿を描いた物語で、広義のミステリのなかでも暗黒小説(ノワール小説)と呼ばれるタイプの作品です。
まず特筆すべきなのは、登場人物たちの抱える孤独と絶望の描写のすばらしさ。貧困や借金、家庭崩壊、DV、介護など、4人の主婦たちをとりまくさまざまな問題と、弁当工場での過酷な労働が緻密に描写され、彼女たちの日常の倦みがいかに深いものであるかが克明に描かれていきます。
そんななかで、彼女たちのひとりが夫を衝動的に殺害し、ほかの3人はその死体処理に関わることで犯罪に加担していきます。そこからは、犯人が最初からわかっているミステリ──いわゆる倒叙もののようなスリルとサスペンスで物語が一気に加速していくのですが、『OUT』がすごいのは、事件が露見していく一般的なミステリのスタイルから完全に逸脱していくところです。
どのように逸脱していくのかについては実際に読んでいただきたいですが、この展開を予想できる読者はそういないでしょう。4人の主婦のなかでも傑出した造形の雅子を主軸に据え、彼女が独自の地平を切り拓いていく壮絶な過程を描ききったところに『OUT』の最大の魅力があると思います。
アメリカでの刊行当時、『OUT』はペーパーバックではない単行本としては異例の売れ行きを見せていたそうで、一般の読者からも高い評価を受けていたことがわかります。2022年には、犯罪小説叢書の老舗であるブラック・リザード社が手がけるアニバーサリーエディションの1冊に選出。ノワール作家として有名なジェイムズ・エルロイが序文で賛辞を寄せているとのことで、その内容をnoteにまとめてくださっている方がいます。
現在においても、アメリカでもっとも評価されている日本人作家のミステリといっていいのかもしれません。
『容疑者Xの献身』東野圭吾
天才数学者でありながら不遇な日々を送っていた高校教師の石神は、一人娘と暮らす隣人の靖子に秘かな想いを寄せていた。彼女たちが前夫を殺害したことを知った彼は、2人を救うため完全犯罪を企てる。だが皮肉にも、石神のかつての親友である物理学者の湯川学が、その謎に挑むことになる。ガリレオシリーズ初の長篇、直木賞受賞作。
(文藝春秋社BOOKSより引用)
『容疑者Xの献身』は、東野圭吾による長編小説です。「ガリレオ」シリーズの第3作目にして初の長編で、日本では2005年に刊行されると、当該年度の主要な3つのミステリランキングすべてで1位を獲得し、さらに第6回本格ミステリ大賞と第134回直木賞を受賞。大ベストセラーとなり、著者の人気作家としての地位を絶対的なものにしました。
アメリカでの英訳版は2011年に刊行され、翌2012年にエドガー賞最優秀長編賞の最終候補にノミネート。日本人作家として史上2度目の快挙となりました。
ストーリーは、高校の数学教師である石神が、隣人の母娘が犯した前夫の殺害を隠蔽するために完全犯罪を企てる倒叙もの。石神は天才といわれた数学者で、かつての親友である物理学者・湯川が探偵役として事件の謎に挑むことになります。まったくの偶然ですが、主要人物が知人の犯罪のために手を貸すという点は『OUT』と同じです。
本作でなんといっても印象に残るのは石神のキャラクターでしょう。かつて天才と称された数学者でありながら、親の介護のために研究者としての道を諦め、いまは半ば死んだように孤独な生活を送る日々。ひそかに想いを寄せる隣人の靖子が働く弁当屋で弁当を買うことだけが、彼のささやかな潤いです。そんななかで靖子とその娘が殺人を犯し、彼女たちの窮地を救うために石神は自身のすべてを擲っていく──『容疑者Xの献身』はもちろんミステリですが、そんな純愛小説としての側面も持っているのです。
そのほかにも、倒叙ミステリとしての緊迫感、変人同士である石神と湯川の友情、かつての親友と闘うことになる湯川の苦渋、そして最後に用意されたどんでん返しなど、『容疑者Xの献身』はさまざま魅力を内包した傑作です。シリーズの第1作目『探偵ガリレオ』と第2作目『予知夢』はどちらも連作短編集で、どちらかといえば小粒な印象でしたが、本作で「ガリレオ」シリーズは一気に化けたといっていいでしょう。
『容疑者Xの献身』は残念ながらエドガー賞の受賞は逃したものの、アメリカ図書館協会最高推薦図書の2012年ミステリ部門に選出されるなど、非常に高く評価されています。大ヒット作なので既読の方も多いかもしれませんが、未読の方にはぜひ手にとってみていただきたいです。
『贖罪』湊かなえ
15年前、静かな田舎町でひとりの女児が殺害された。直前まで一緒に遊んでいた四人の女の子は、犯人と思われる男と言葉を交わしていたものの、なぜか顔が思い出せず、事件は迷宮入りとなる。娘を喪った母親は彼女たちに言った──あなたたちを絶対に許さない。必ず犯人を見つけなさい。それができないのなら、わたしが納得できる償いをしなさい、と。十字架を背負わされたまま成長した四人に降りかかる、悲劇の連鎖の結末は!?
(双葉社HPより引用)
『贖罪』は、湊かなえによる長編小説です。日本では2009年に刊行、英訳版は2017年に出版され、翌2018年にエドガー賞の最優秀ペーパーバック・オリジナル賞の最終候補にノミネートされました。『OUT』『容疑者Xの献身』がノミネートされた最優秀長編賞はハードカバーが対象でしたが、『贖罪』はペーパーバックで発売されたため部門が異なります。
女子小学生が犠牲になった15年前の殺人事件において犯人を目撃した4人の同級生と、被害者の女の子の母親が主要人物で、章ごとに語り手がわかる独白形式で書かれています。この独白形式といい、いわゆる「イヤミス」的な作風といい、著者のデビュー作にして大ヒット作である『告白』を想起させるところの大きい作品です。
かつての事件が主人公たちのその後の人生にいかに影を落とし、彼女たちをさらなる事件へ導いていったのか、章が変わるたびに新たな悲劇が語られるため、各章の読後感は常に重いものがあります。迷宮入りした15年前の事件の真相が少しずつ浮かび上がってくる構成も、ミステリとしてのリーダビリティを保証してくれます。
ただ、悲劇の連鎖といえばそうなのですが、あまりに多くの事件が起きるのと、意図的にイヤミス的な要素を強調しているような部分があり、リアリティには若干欠けるようにも思います。個人的には、湊作品のなかではイヤミス的なものより、『ブロードキャスト』のように作者の趣味・嗜好がストレートに出ている小説のほうが好きなので、少し評価が辛めになった点は否めません。とはいえ、『告白』に通ずる要素の多い作品なので、『告白』が好きな方なら読んで損する可能性は低いでしょう。
ちなみに、『贖罪』の前には『告白』の英訳版も英米で出版されており、『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙で2014年ミステリベスト10の1作に選ばれたり、全米図書館協会アレックス賞(「ヤングアダルト世代に薦めたい一般書」に授与される賞)を受賞したりと、高い評価を得ています。
そのほかのエドガー賞と日本人の関わり
上記の小説3作以外にも、日本人の作品がエドガー賞にノミネートされた例が2つあります。
ひとつは、黒澤明の映画『天国と地獄』で、1964年のエドガー賞最優秀外国映画賞にノミネートされました。原作はエド・マクベインの小説『キングの身代金』です。
もうひとつは、米文学者で北海道大学大学院教授、竹内康浩が書いた『マークX 誰がハック・フィンの父を殺したか』です。マーク・トゥエイン『ハックルベリー・フィンの冒険』についての研究書で、2019年に評論・評伝部門にノミネートされました。これは2015年に日本で刊行した『謎とき『ハックルベリー・フィンの冒険』: ある未解決殺人事件の深層』をもとに、新資料を加えて英語で書き下ろしたものです。まったく同じものではないですが、ベースになった本は日本語で読めますので、興味のある方はぜひご一読ください。
まとめ
以上、エドガー賞にノミネートされた日本人作家の作品の紹介でした。いずれも受賞は逃しているものの、全体として翻訳作品の受賞するケースは少ないため、ノミネートされただけでも快挙といえます。そんな快挙を成し遂げた小説がどのようなものなのか、気になる方は手にとっていただければと思います。