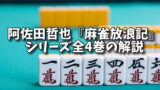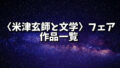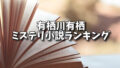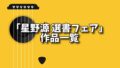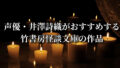麻雀に関する本は、打ち方を勉強するための戦術本が圧倒的に多いと思いますが、数は少ないながら麻雀小説もあります。この記事では、往年の名作から超人気作家の長編、現役Mリーガーの初小説、異色の麻雀SFまで、おすすめの麻雀小説を紹介いたします。
麻雀に詳しい方はもちろん、そうでない方にも楽しめる部分はきっとあるはずだと思いますので、参考にしていただければ幸いです。
『麻雀放浪記』阿佐田哲也
敗戦直後、焦土と化した東京で、全てを失った“坊や哲”。戦中の勤労動員で知り合った“上州虎”と再開し、博打世界へ入り込んでいく。チンチロ博打の賭場で出会った“ドサ健”や、凄腕のバイニン“出目徳”との出会いを通じて、麻雀打ちとして生きることになった坊や哲。麻雀に生きる男たちを描くピカレスクロマンの大傑作。
(双葉社公式より引用)
『麻雀放浪記』は、阿佐田哲也による麻雀小説のシリーズです。麻雀小説の原点にして頂点というべき大傑作で、まずはこれを読まないことには始まりません。敗戦まもない昭和20年から30年ごろまでを舞台とし、賭け麻雀の世界に生きる主人公の坊や哲が、さまざまな個性を持ったライバルたちとしのぎを削るピカレスクロマン。この作品以上に、命をなげうつようなすさまじい激闘を描いた麻雀小説はないでしょう。
シリーズは「青春編」「風雲編」「激闘編」「番外編」の全4巻で、いずれも非常におもしろいですが、個人的には最初の2巻である「青春編」「風雲編」がとくにおすすめです。著者の阿佐田哲也は「雀聖」とも呼ばれた戦後日本の麻雀文化における超重要人物で、ほかにも麻雀小説を多数書いているので、『麻雀放浪記』を読み終わったらそれらに手を伸ばすのも楽しいと思います。
なお、『麻雀放浪記』全4巻については、以下の記事で詳しく紹介しています。よろしければあわせてお読みください。
『病葉流れて』白川道
十八の春、大学に入った梨田雅之にとってすべてのものが未知だった。酒場も、そして女も。だが、運命的に出逢った麻雀に、梨田はその若さを激しくぶつける。次第に彼は博打こそ自分の天運と対峙するものと考え、この道で生きていくことを決意する。そして果てしなき放蕩の日々が始まった──。無頼派作家が描く自叙伝的ギャンブル小説の傑作!
(幻冬舎plusより引用)
『病葉流れて』は、ハードボイルド作家・白川道による麻雀小説です。『天国への階段』などで知られる著者ですが、本作は実体験に基づく自伝的小説といわれています。田舎から上京してきた平凡な大学生の主人公が、賭け麻雀の世界にどうしようもなくのめりこんでいく──その昏くひりつくような緊張感や金銭感覚が狂っていくさまが描かれているのですが、これが事実だと思うとなかなかすごい人生です。
本格的な麻雀小説としては、(阿佐田哲也の諸作を除けば)『麻雀放浪記』に次ぐ秀作といっていい作品だと思います。物語の舞台こそ『麻雀放浪記』より少しあとの時代になりますが、昭和の香りが漂う青春小説という点も共通しており、読み比べてみるのも楽しいでしょう。
続編に『朽ちた花びら 病葉流れて2』『崩れる日なにおもう 病葉流れて3』の2作があり、さらに『新・病葉流れて』と銘打ったシリーズが計4作発表されています。
『渚のリーチ!』黒沢咲
ITコンサルタントの仕事をしながら、大好きな麻雀に日々打ち込む渚は、麻雀のプロテストを受ける決心をする。会社員とプロを両立するハードさも、手痛い失敗や挫折も糧にして、一歩ずつ自分だけの雀風を確立していく渚。ある日彼女のもとに、大規模なナショナルリーグ設立の噂が舞い込みー。初代Mリーガー、日本プロ麻雀連盟A1リーガーとして躍動し続ける著者が、麻雀をもっと好きになりたいすべての人へ贈る物語。”
(「BOOK」データベースより引用)
『渚のリーチ!』は、現役のプロ雀士・黒沢咲による麻雀小説です。プロ野球選手が野球小説、Jリーガーがサッカー小説を書くようなもので、非常に珍しい成り立ちの作品だと思います。
Mリーガーとしても活躍する著者の実体験をベースにしたストーリーで、現代の競技麻雀の世界を描いたものなので『麻雀放浪記』や『病葉流れて』のようなギャンブル小説の要素はいっさいありません。青春小説としての読み味もさわやかそのものです。
さすがにプロの作家の作品ほど小説としての完成度が高いわけではありませんが、現役プロ雀士による小説がどのようなものか、気になる方は手にとってみてもいいと思います。
『砂漠』伊坂幸太郎
入学した大学で出会った5人の男女。ボウリング、合コン、麻雀、通り魔犯との遭遇、捨てられた犬の救出、超能力対決……。共に経験した出来事や事件が、互いの絆を深め、それぞれを成長させてゆく。自らの未熟さに悩み、過剰さを持て余し、それでも何かを求めて手探りで先へ進もうとする青春時代。二度とない季節の光と闇をパンクロックのビートにのせて描く、爽快感溢れる長編小説。
(新潮社HPより引用)
『砂漠』は、伊坂幸太郎による青春小説です。「麻雀小説」というほど麻雀がメインのお話ではないのですが、主人公を含む大学生たちが麻雀に興じる様子がたびたび描写されています。主要登場人物の苗字が「東堂」「南」「西嶋」「北村」「鳥井」となっていて、それらが字牌の「東南西北」と「一索」を表していることからも、著者のなかで麻雀がこの物語のキーワードだという意識があったことは間違いないでしょう。
ストーリーとしては個性的なキャラクターたちの大学生活を描くさわやかな青春小説であり、伊坂幸太郎らしいユーモアや伏線回収の妙もあって、麻雀の要素抜きでも楽しい一作になっています。
『祈れ、最後まで』鷺沢萌(『祈れ、最後まで・サギサワ麻雀』所収)
鷺沢萠の愛した世界、最初で最後の麻雀作品集。没後に発見された中編小説「祈れ、最後まで」未発表・完全版、笑って泣ける痛快エッセイ「サギサワ麻雀」を収録!!
(竹書房公式より引用)
「祈れ、最後まで」は、鷺沢萌による中編小説です。2004年に35歳の若さで亡くなった著者は、青春小説や恋愛小説の書き手というイメージが強いですが、じつは大の麻雀好きで知られる人物でもありました。「祈れ、最後まで」は没後に発見された中編小説で、彼女が唯一遺した麻雀小説です。
主人公の和正は、大学卒業後も就職した信用金庫をとある事情から半年足らずで辞め、現在はフリー雀荘で働いている若者です。「雀ゴロ」だった父の影響で、かつては麻雀にのめりこんでいたこともありますが、現在はそれほどの情熱もなく、雀ボーイとして客と打つ程度。そんな彼に対し、ある日店の客としてやってきた安田という男が「麻雀を教えてやる」と話を持ちかけてきて──というのがあらすじです。読後に静かな感動の残る青春麻雀小説として、ぜひ一読をおすすめしたい佳品です。
また、単行本に併録されている「サギサワ麻雀」は、軽妙なノリの麻雀エッセイ集。麻雀好きの共感を呼ぶ泣き笑いのエピソードが数十本収録されています。
『清められた卓』宮内悠介(『盤上の夜』所収)
彼女は四肢を失い、囲碁盤を感覚器とするようになった──。若き女流棋士の栄光をつづり、第1回創元SF短編賞で山田正紀賞を贈られた表題作にはじまり、同じジャーナリストを語り手にして紡がれる、盤上遊戯、卓上遊戯をめぐる6つの奇蹟。囲碁、チェッカー、麻雀、古代チェス、将棋……対局の果てに人知を超えたものが現出する。デビュー作品集ながら直木賞候補となり、日本SF大賞を受賞した、2010年代を牽引する新しい波。
(東京創元社HPより引用)
「清められた卓」は、宮内悠介による短編小説です。囲碁や将棋など盤上遊戯を扱う作品ばかりを集めたデビュー短編集『盤上の夜』に収録されている一編で、麻雀については著者自身がプロ級の腕前とのこと。
舞台となるのは、プロ・アマ混合のタイトル戦“第9回白鳳位戦”の決勝戦。対局のあまりの異質さ、異様さゆえに、新日本プロ麻雀連盟の歴史から抹殺されたという異形の一戦の顛末が描かれます。
決勝戦を戦うのは以下の4人。〈都市のシャーマン〉を名乗る新興宗教の教祖で、統合失調症患者の真田優澄。4人のなかで唯一のプロ雀士で、過去の事故の影響で前向性健忘症を患っている新沢駆。アスペルガー症候群かつサヴァン症候群の天才少年・当山牧。優澄の元恋人かつ元主治医で、彼女を追って勝ち上がってきた精神科医・赤田大介。
〈シャーマン〉を名乗るにふさわしい魔術的な打ち方をする優澄を中心に、4人は互いに譲らぬ激闘を繰り広げます。引き締まった文体、対局シーンの緊迫感、奇想と感動が融合する結末と、いずれの要素も隙がなく、短編ではありますが『麻雀放浪記』に比肩する麻雀小説の大傑作だと思います。「清められた卓」のみならず、『盤上の夜』の収録作はどれも非常にレベルが高いので、ぜひ手にとってみていただきたいです。
なお、本作を含め、ボードゲームを扱った宮内悠介の小説について以下の記事にまとめておりますので、よろしければあわせてお読みください。
『接待麻雀士』新川帆立(『令和反逆六法』所収)
六つのパラレル・レイワ、六つの架空法律で、現行法と現実世界にサイドキック! 「命権擁護」の時代を揺さぶる被告・ボノボの性行動、「自家醸造」の強要が助長する家父長制と女たちの秘密、「労働コンプライアンス」の眩しい正義に潜む闇……。痛烈で愉快で洗練された、仕掛けだらけのリーガルSF短編集。
(集英社HPより引用)
「接待麻雀士」は、新川帆立による短編小説です。元弁護士で、元プロ雀士でもあるという著者の異色の経歴が存分に活かされた一編です。架空の法律が施行された世界を舞台にした短編集『令和反逆六法』に収録されています。
舞台は賭け麻雀が合法化された日本。それによって政治家や官僚に適法に賄賂を渡すための賭け麻雀が横行しており、各企業はそのために接待麻雀士を雇っています。主人公の塔子はプロ雀士から接待麻雀士に転向した麻雀打ちで、巧みに負けることで相手に金を渡すのが彼女の仕事です。
しかし、ある日塔子がいつものように接待麻雀を打とうすると、相手がそれを拒むように不可解な打ち方をしてきます。賄賂を受け取る側がなぜ勝つのを避けるのか。接待麻雀の裏に隠された意外な真実が明らかになる、SF設定の麻雀ミステリとなっています。短編集収録作のなかでも出色の作品なので、一読をおすすめいたします。
『シャングリラ』張系国(『星雲組曲』、米澤穂信編『世界堂書店』所収)
タイムマシン、人工生命体、異星間通訳などSF的設定と幻想の中に人類の未来や社会批評までを盛り込んだ連作『星雲組曲』『星塵組曲』を収録。台湾SF小説を初めて本格的に紹介する。
(国書刊行会HPより引用)
「シャングリラ」は、台湾のSF作家・張系国による短編小説です。海外にも麻雀が登場する小説がまれにありますが(もっとも有名なのはアガサ・クリスティ『アクロイド殺し』でしょう)、麻雀がアイデアの中核にある海外小説は私が把握しているかぎりでは「シャングリラ」が唯一です。
15ページにも満たない短い作品なので、麻雀がどのようにストーリーに関わっているか説明してしまうとネタバレになってしまうのですが、宇宙規模のスケールを持ったバカSF(もちろん褒め言葉)として非常に楽しい逸品です。
国書刊行会から出ている短編集『星雲組曲』に収録されていますが、人気作家・米澤穂信が編んだアンソロジー『世界堂書店』でも取りあげられているため、後者のほうが安価に入手できるでしょう。
まとめ
以上、長編・短編合わせて8つの麻雀小説を紹介いたしました。おもしろい麻雀小説を探している方の一助になれば幸いです。