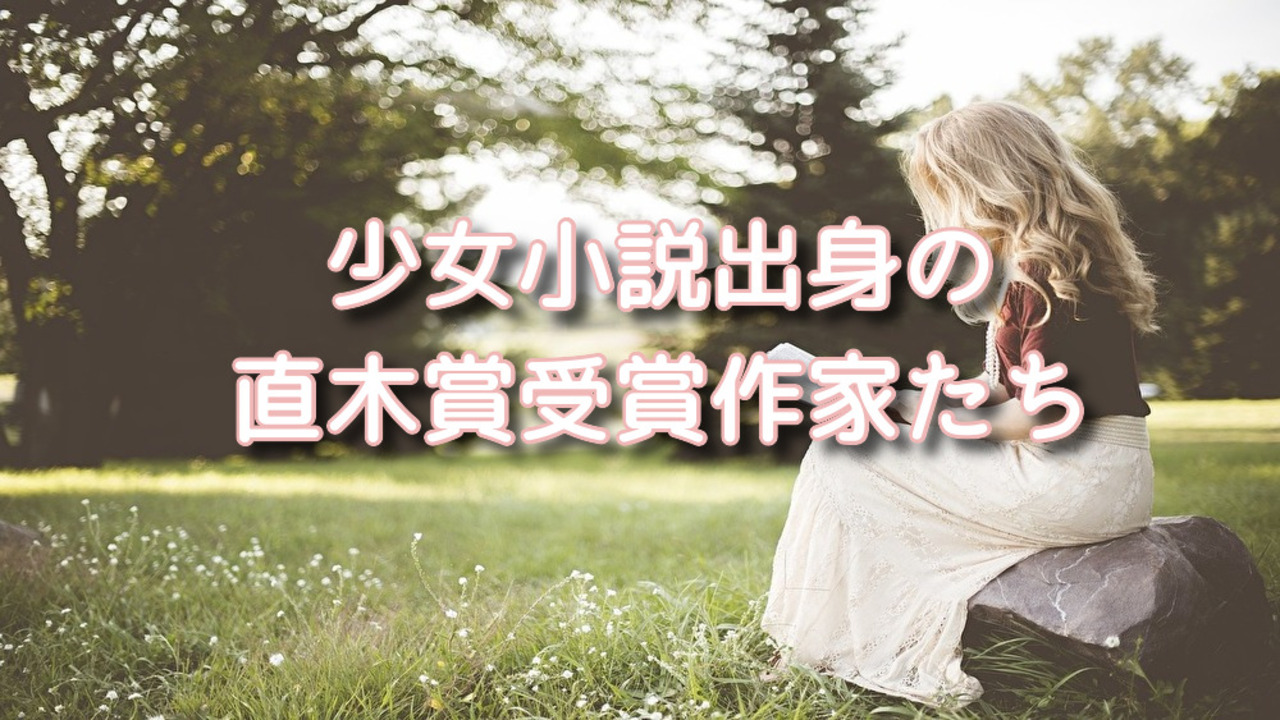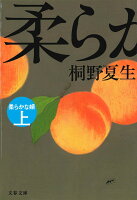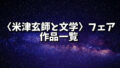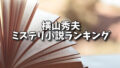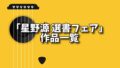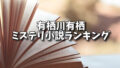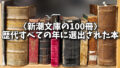この記事では、少女小説の書き手としてキャリアをスタートさせ、のちに直木賞受賞を果たした作家について紹介していきます。
「少女小説」とひと口にいってもそのイメージは人それぞれだと思いますが、ここでは集英社コバルト文庫や講談社X文庫ティーンズハートといったレーベルから出ていた作品と定義します。「少女向けライトノベル」と呼んでもいいのですが、「ライトノベル」という言葉が誕生する以前にデビューしている作家について扱うため、「少女向けライトノベル出身」というより「少女小説出身」のほうがふさわしいと判断しました。
なお、ライトノベル出身の直木賞受賞作家については下記の記事で紹介しています。よろしければあわせてお読みください。
桐野夏生
桐野夏生は1984年、『愛のゆくえ』で第2回サンリオロマンス賞に佳作入選し、小説家としてデビューします。この作品は『ロマンス傑作集』という5冊セットで販売されたうちの1冊に収録されています。今では非常に入手困難な本で、残念ながら筆者も読んだことはありませんが、当時の筆名は現在と同じ「桐野夏生」となっています。
(当ブログでは楽天から商品画像を取得しているのですが、『ロマンス傑作集』が楽天で取り扱われていないため、画像つきリンクを作成することができません。かわりにAmazonのテキストリンクを貼っておきますので、こちらからどうぞ⇒『ロマンス傑作集』)
その後、彼女は1989年発表の『恋したら危機(クライシス)!』から野原野枝実名義を用い、作家活動を行っていきます。同作は主人公の女の子が全寮制の男子校に入学してしまい、男装女子として学校生活を送るというストーリー。まるで少女漫画の『花ざかりの君たちへ』のようですが、もちろん本作のほうが発表は先です。
デビューから野原野枝実名義で活動していた時期までのことは、その後の諸作品の著者プロフィールにも記載されておらず、今では「なかったこと」に近い扱いとなっています。本人にとってはあまり思い返したくない歴史なのかもしれません。
「桐野夏生」の名前が世間にふたたび登場するのは1993年のこと。『顔に降りかかる雨』で第39回江戸川乱歩賞を受賞し、彼女は「再デビュー」を果たします。女流ハードボイルド作家・桐野夏生が誕生した瞬間でした。少女小説家時代からは大きく作風を変え、1997年には衝撃的な犯罪小説『OUT』で大きな話題を呼びます。
そんな桐野夏生の直木賞受賞作は、1999年発表の『柔らかな頬』です(第121回/1999年上半期)。不倫のさなかに幼い娘を失踪というかたちで失った母親が主人公で、目を背けたくなるような容赦のない内容のためかなり読者を選ぶ小説ではありますが、濃密な心理描写にぐいぐい引きこまれる傑作です。重たい作品に抵抗のない方はぜひご一読を。
唯川恵
唯川恵は1984年、中編「海色の午後」で第3回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビューします。システムエンジニアとして働くOLが主人公で、恋愛、結婚、仕事、親子関係のなかで揺れ動く若い女性の心情を描いた作品です。『コバルト・ノベル大賞入選作品集2』に収録されていますが、2004年に単著として集英社文庫に収録されたため、そちらのほうが入手しやすいでしょう。書き下ろしのあとがきもうれしいところです。
彼女の少女小説家時代は、1990年代初頭まで続きます。この時期の作品は現在では入手しにくいものが多いですが、『ためらいがちのシーズン』など一部のちに復刊されているものもあります。
一般文芸における唯川恵の最初の作品は、1988年の『22歳、季節がひとつ過ぎていく』です。この長編は「角川文庫・緑帯」から独立した「角川文庫・青帯」のレーベルで書き下ろしとして出版されました。「青帯」は1989年にレーベル名が「角川スニーカー文庫」と正式に決まります。スニーカー文庫といえば現在ではライトノベルのレーベルですが、『22歳、季節がひとつ過ぎていく』が発売された当初はまだそのような位置づけではなかったため、同作が一般文芸での最初の作品と考えていいでしょう。現在では新潮文庫でも読めますが、幻冬舎文庫版が新刊で入手可能(2025年1月現在)なので、そちらのリンクを貼っておきます。
その後恋愛小説のほか、ホラーやサスペンス系の作品も手がけていきますが、文学賞の受賞どころか、ノミネートすら一度もない時期が続きます。しかし2001年、正反対の女性ふたりの恋愛と友情を描いた長編『肩ごしの恋人』で初めての直木賞の候補になると、そのまま受賞(第126回/2001年下半期)。キャリア17年目にして初の文学賞受賞が直木賞という快挙を達成したのでした。
山本文緒
山本文緒は1987年、中編「プレミアム・プールの日々」で第10回コバルト・ノベル大賞の佳作を受賞し、作家デビューを果たします。コバルト文庫では他の作家の作品とあわせて、『コバルト・ノベル大賞入選作品集5』に収録されています。しかし、同じくコバルト文庫の『おひさまのブランケット』がのちに集英社文庫で復刊された際に「プレミアム・プールの日々」も併録されたため、現在はそちらのほうが入手しやすいでしょう。
「プレミアム・プールの日々」は中編だったため、1冊の本として最初に出版されたのは1988年の長編『きらきら星をあげよう』になります。少女小説の王道というべきか、少女漫画のようなノリで楽しめる軽妙な青春恋愛小説です。この作品ものちに集英社文庫で復刻されました。山本文緒の少女小説時代の作品は、すべてというわけではないですが、一般文芸の文庫レーベルで復刊されたものがいくつかあります。当時を振り返るあとがきも書き下ろされているので、ファンとしてはうれしいところです。
やがて彼女はコバルト文庫を離れると、1992年の『パイナップルの彼方』から一般文芸へシフト。同作は平凡なOLの日常を舞台としながら、巧みな人物描写でじつにスリリングな傑作です。さらに1998年には、生半可なホラーよりよほど恐ろしい恋愛小説『恋愛中毒』を発表し、第20回吉川英治新人文学賞を受賞して話題を呼びます。
『恋愛中毒』で文壇での評価も獲得した彼女は、2000年発表の『プラナリア』で直木賞受賞を達成します(第124回/2000年下半期)。それぞれの理由で「無職」という境遇にある女性たちを主人公にした5編収録の短編集です。ときにわがままだったり自堕落だったりする主人公たちの心情を丁寧に掬いあげ、山本文緒が「普通の人々」の弱さやズルさにいつも寄り添ってきた作家だということを実感させてくれる作品集となっています。
角田光代
角田光代は1988年、中編「お子様ランチ・ロックソース」で第11回コバルト・ノベル大賞の大賞を受賞し、彩河杏名義で作家デビューします。山本文緒の1年後輩にあたり、先述の『コバルト・ノベル大賞入選作品集5』にはふたりの作品が同時に収録されています。のちの活躍を考えるとずいぶん豪華な作品集といえそうです。
単著としてのデビュー作は、『胸にほおばる、蛍草』という長編です。異母姉妹の女性ふたりの物語らしいのですが、古本でも非常に入手が難しい作品で、筆者は読んだことがありません。同作にかぎらず、彩河杏名義の作品はすべて絶版で復刊もなく、古本市場でも高騰している稀少本ばかり。彼女自身この時代のことを語ることは少なく、今後復刊される可能性もほぼないと思われます。
彼女の少女小説家時代は2年足らずと短く、1990年に「幸福な遊戯」で第9回海燕新人文学賞を受賞し、角田光代と名義も改めて純文学作家として再スタートを切ります。芥川賞にも複数回ノミネートされながら、1996年には『まどろむ夜のUFO』で第18回野間文芸新人賞を受賞。初期の角田作品はモラトリアムを生きる若者たちの不安や迷いを描き、「アパート文学」「フリーター文学」などとも称されました。
同時に児童文学も手がけるようになり、1999年発表の『キッドナップ・ツアー』では小学5年生の女の子と父親を軽やかに描き、第46回産経児童出版文化賞フジテレビ賞と第22回路傍の石文学賞を受賞します。
純文学以外に活躍の場を広げるなかで今度は芥川賞ではなく直木賞の対象となり、一度候補になったあと、2004年発表の『対岸の彼女』で見事受賞を射止めました(第132回/2004年下半期)。専業主婦の小夜子と、彼女の就職先となるベンチャー企業の女社長・葵。一見正反対に見えるふたりの女性を軸に、女性同士の関係性や人間模様を描いた傑作です。
まとめ
以上、少女小説出身で直木賞を受賞した作家4名の紹介でした。彼女たちのような優れた才能を発掘したことは、少女小説が果たした大きな功績のひとつだと思います。 気になった作家、作品があればぜひ読んでみてください。